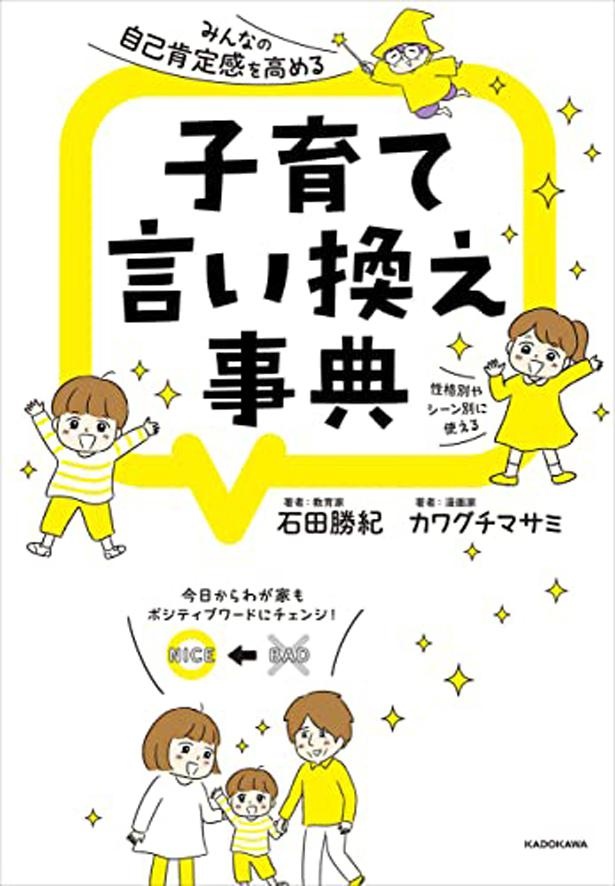「ねえねえ、聞いて」としつこく話しかけてくる子へかける言葉は?/子育て言い換え事典(12)

「ゲームや動画に夢中になってしまう」「口答えや言い訳ばかり言う」「宿題を解くのに時間がかかる」…子どもたちがこんな状況の時、どのような声かけをしていますか?
親の言葉が知らず知らずのうちに子どもの心を傷つけ、自己肯定感を下げてしまっていることがあります。ついつい言ってしまいがちが「ネガティブワード」を、どのような「ポジティブワード」に言い換えればいいのでしょうか。
これまで5万人以上の生徒を指導し、全国で保護者の相談に応えてきた教育専門家の石田勝紀氏が、実際に行ってきたアドバイスとその成果をもとに、子どもへの適切な声かけを「場面別」「性格別」にわかりやすくまとめました。
ご自身も育児に奮闘中の漫画家・カワグチマサミさんのイラストで、子どもの自己肯定感を高める言葉の選び方をご紹介します!
※本作品は石田 勝紀、カワグチ マサミ著の書籍『みんなの自己肯定感を高める 子育て言い換え事典』から一部抜粋・編集しました。
「ねえねえ、聞いて」としつこく話しかけてくる子へ

あいまいなメッセージを少し具体的にすると子どもの理解度がグンとあがります
私が主宰する「Mama Café(ママカフェ)」コミュニティでオンラインのお話し会をしていたときのこと。画面のむこうで、5歳くらいの娘さんがお母さんの横に立ち、話しかけている姿が見えました。「ねぇママ? おやつは?」と何度も何度も質問。お母さんは「ちょっと待ってね」と伝えますが、それでもあきらめません。ずっと「ママ、おやつは?」と繰り返すのです。そこで私は思わず笑って、「そのしつこさ、すごくいいよ! 早くお菓子をあげて」と伝えたのでした。
「しつこさ」はあきらめない心を持っている証。勉強でもスポーツでもしつこくやり続けるのはとても重要で、しつこい子のほうが成果を出しやすかったりします。
とはいえ、日常の中で、しつこく何度も話しかけられたり、お願いされたりすると困る場面もあるでしょう。そんなときに使われる「ちょっと待ってね」「あとでね」は、残念ながらあまり効果を期待できません。「ちょっと」の感覚は人によって異なるからです。親にとっては「5分後」でも、その子にとっては「5秒後」かもしれません。
「ちょっと」や「あとで」を子どもが理解できる具体的なメッセージに変換する必要があります。時計を見せながら「この長い針が3を指したらね」「この洗い物が終わったら」というように具体的な数字やアクションで説明すると伝わりやすくなります。
短所と長所のとらえ方
( 短所)しつこい
ではなく、
↓
( 長所)あきらめない心を持っている
ということ!
自己肯定感を高めるワンポイント
スポーツなど「自分自身に関わること」であればよいのですが、お友だちへの嫌がらせを何度もやってしまうなど、しつこさが「他人に向けられたもの」の場合は止める必要があります。そんなときは「嫌がっているんだから、やめなさい」と命令の声かけが〇。命令形は緊急事態で発する言葉。めったに使わないからこそ、使ったときに効力を発揮します。
ポイント
日常の子育てでは「命令形」の声かけを極力控え、子どもの行動を止めるべき緊急事態で使う
著=石田 勝紀、カワグチ マサミ/『みんなの自己肯定感を高める 子育て言い換え事典』(KADOKAWA)
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「アルジタル デリケートハイジーンソープ」」
刺激に弱いデリケートエリアをやさしく洗う、オーガニックソープ
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
コミックエッセイランキング
コミックエッセイをもっと見る
作品を検索する
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細