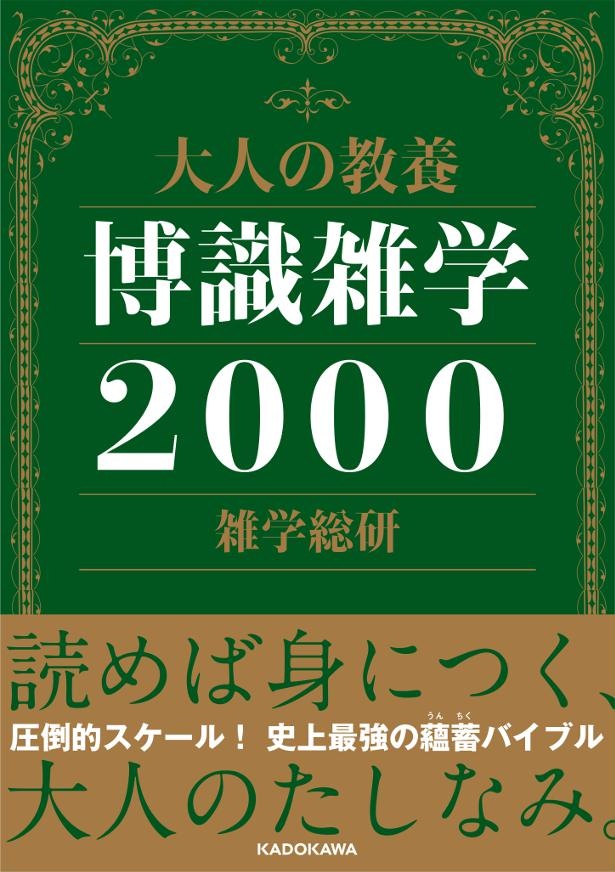「木彫りのクマ」はなぜ、北海道土産の定番になった?/大人の教養 博識雑学2000(37)
京都には「銅閣」も存在する!?
地球は毎年5万トンずつ軽くなっている!
牛乳は季節によって味が違う!?
などなど、 あなたは知っていましたか?
知っていると思わず誰かに話したくなる、文化・社会・サイエンス・地理・歴史・ワールド・芸術・生活・スポーツなど、古今東西の幅広いジャンルの雑学ネタをたっぷりご紹介します。情報にあふれた今の世の中で知っておきたいお役立ち情報が満載。
文系理系じゃくくれない「大人の教養」が、日々の会話やちょっとした雑談に役立つはずです!
※本記事は『大人の教養 博識雑学2000』から一部抜粋・編集しました。
「木彫りのクマ」がなぜ北海道土産の定番になったのか

北海道土産の定番といえば、鮭をくわえた「木彫りのクマ」である。その発祥の地として知られるのが、室蘭と函館の中間あたりに位置する八雲町(やくもちょう)。旧尾張藩主の徳川慶勝(よしかつ)が、1878(明治11)年、生計を立てさせるために旧藩士を移住させて開拓した尾張徳川家ゆかりの地だ。
1921(大正10)年、慶勝の後継者にあたる義親(よしちか)がヨーロッパ旅行に行った際、スイス土産として木彫りのクマを持ち帰った。義親は、町内で働く農民たちに、冬の間の副業として木彫りの工芸品をつくることを提案する。
スイス土産のクマを手本にし、翌年、酪農家の伊藤政雄が木彫りのクマ第1号を製作。以来、八雲は木彫りのクマの産地となっていった。
これが昭和初期に各地に流通した際、旭川のアイヌの人々に影響を与え、ここでつくられる「鮭をくわえたクマ」の形が一般化したのだ。
著=雑学総研/『大人の教養 博識雑学2000』(KADOKAWA)
Information
おすすめ読みもの(PR)
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細