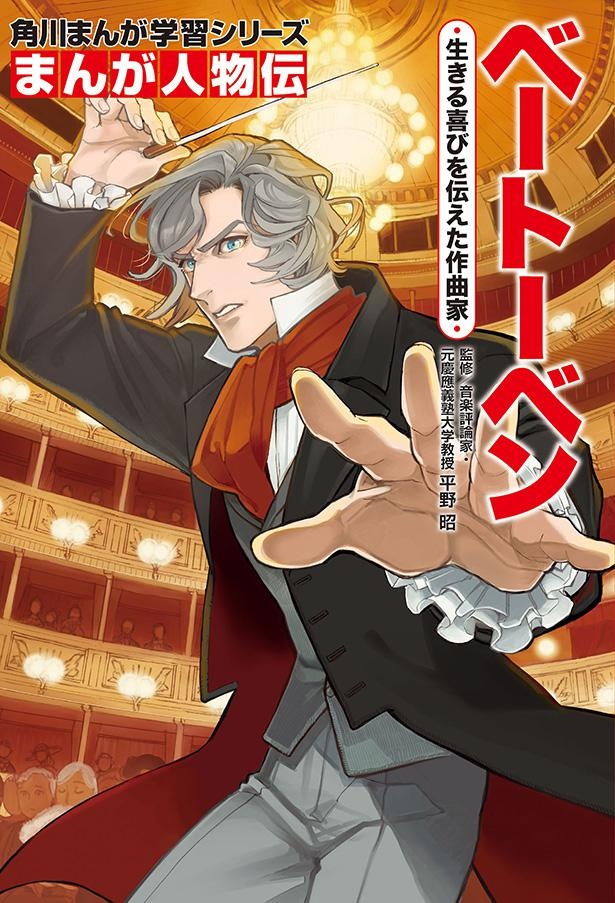200年前の生活をのぞき見!? 『ベートーヴェン捏造』著者に聞く当時の「会話帳」の魅力

9月12日(金)に公開される映画『ベートーヴェン捏造』。しがないヴァイオリニストだったシンドラー(山田裕貴)が、ある日少年時代から憧れの音楽家・ベートーヴェン(古田新太)に出会い、秘書となって働くことに。そこで初めて知ることになるベートーヴェンの真実の姿とは――
ベートーヴェンとその周辺人物の超ドロドロな(!?)人間関係に迫る本作。その鍵となるのは、ベートーヴェンが晩年に使っていた筆談用の「会話帳」です。今回は、映画の原作本『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(河出文庫)の著者・かげはら史帆さんに、会話帳から読み取れるベートーヴェンの日常生活について詳しくお話を聞きました。
登場人物全員キャラ立ちすぎ!? 「ベートーヴェン周辺人物オタク」になったわけ

――まずは、かげはらさんがベートーヴェンやそのまわりの人物に興味を持つようになったきっかけを教えてください。
かげはら史帆さん:きっかけは高校1年生のとき。音楽の授業で映画『アマデウス』を観たんです。モーツァルトとサリエリの確執を描いた有名な映画ですが、そこでクラシック音楽家の人間関係や人物像に萌えてしまって。それ以来、音楽を聴くというよりも、音楽家の伝記を読み漁るようになりました。
そんな中で出会ったのが、森雅裕さんの小説『モーツァルトは子守唄を歌わない』(講談社)でした。ベートーヴェンと弟子のチェルニーが、モーツァルトの死の謎を解くというミステリーなんですが、これにもうどハマりして! ベートーヴェンの伝記や周辺の人物について詳しく調べるようになったんです。
大学ではドイツ語を学んでいたので、少しずつドイツ語の原文も読めるようになってきて、ついには「会話帳」と呼ばれるベートーヴェンの日常の記録にまで手を伸ばすようになり、今に至るという感じです。
――10代でクラシック音楽家の人間関係に目をつけるというのが面白いですね。
かげはら史帆さん:私は音楽の世界よりも、どちらかというとオタクコミュニティに属していた学生だったんです。よく、新選組が好きな人が登場人物の関係性にハマったりするじゃないですか。そんな感じのクラシック音楽家バージョンと思ってもらえればわかりやすいかもしれません。深掘りしていくと、みんなキャラが立っていて本当に面白いんですよ(笑)。
ベートーヴェンの“会話帳”をテーマにした修士論文がノンフィクションに

――著書の『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』は、もともと大学院の修士論文だったそうですね。一般書として出版されるまでには、どんな経緯があったんでしょうか?
かげはら史帆さん:当時からベートーヴェンの会話帳を熟読していたので、好きが高じて修士論文のテーマになったという感じです。でも修論って、大学院に提出したらそれで終わりじゃないですか。「このネタ、絶対に面白いはず!」って自信だけはあったのに、このまま誰にも読まれないのはもったいないなって。なので、社会人になってからもずっと、いつか何らかの形で世の中に出せたら…という思いは持っていました。
そして、大学院を出て10年近く経った頃、とある編集者の方とご縁があって、「これ、本にしましょう」と言っていただけたんです。学術書ではなく、小説のように読めるノンフィクションにしようということで、論文では“会話帳”が主役だったのを、本にするにあたって “人間”を主役にしました。そこで、ベートーヴェンの側近だったアントン・シンドラーを軸にして、彼の人生や心情をえがくような形に仕上げていきました。

――“会話帳”から“シンドラー”へと主役が変わったことで、物語の広がりも出てきたんですね。そもそもベートーヴェンの「会話帳」って、どういうものなんですか?
かげはら史帆さん:「会話帳」とは、ベートーヴェンが晩年に使っていた筆談用のノートのことです。彼は40代後半には聴力がかなり衰えてしまって、人との会話が難しくなっていたんですね。そこで、周囲の人たち――家族や友人、秘書、仕事仲間など――が、彼との会話のためにノートに文字を書いてやりとりしていたんです。使われていたのは1818年から彼が亡くなる1827年までの約10年間で、現存するものだけでも139冊あります。でも実際は、もっと多かったはずだといわれています。
――そんなにたくさん! それだけでかなりの情報が詰まっていそうですね。
かげはら史帆さん:ただ、そこにベートーヴェン本人の書き込みは、ほとんどないんです。なぜかというと、彼は耳が聞こえなくなっても、喋ることはできたから。だから、周りの人はノートに質問や返事を書き、ベートーヴェンはそれを読んで、口頭で答える。そのため、ノートには相手の言葉だけが残っているんです。 だからこの会話帳は、「相手の言葉」から「ベートーヴェンが何を言ったか」を想像しないといけないという、ちょっと変わったテキストなんです。空白をどう埋めるか――そこに面白さがあるんですよね。
ベートーヴェンの日常や人間関係が丸見え!? “会話帳”の中身とは

――ベートーヴェンの会話帳には、どんなことが書かれていたんですか?
かげはら史帆さん:ベートーヴェンといえば大作曲家ですから、「きっと芸術論や音楽談義がぎっしり詰まっているんでしょう?」と思われる方も多いと思うんです。でも、実際に中をのぞいてみると、生活感たっぷり。たとえば「今日の食事は何にする?」とか、「これを買ってきて」みたいなやりとりから、ちょっとしたうわさ話まで、会話帳の中身は、まさに“ベートーヴェンの日常”そのもの。もちろん、芸術家らしい真面目なやりとりも時にはありますが、それはごく一部。むしろ彼の人間らしさや、当時の生活の様子が見えてくるのが、この会話帳の面白いところなんです。その一部をご紹介しますね。
●食事中のやりとり
書いた人:友人たち(1818年)
「若鶏がそこにありますが、いかがですか」
「ペーテルスが訊いてます、牡蠣を食べたいかって」
「このワインは口に合いますか? 他のワインにしましょうか?」
かげはら史帆さん:会話帳には、食べ物の話題がかなりの頻度で出てきます。これはおそらく、居酒屋やレストランのような場所でのやりとり。若い友人たちが、料理をすすめたり味の感想を聞いたりしていて、当時の人たちの食生活を垣間見ることができます。単なる雑談に見えて、実は文化史や食の歴史の資料としてもすごく価値があるんですよ。実際、そうした視点で研究している本も出ています。

●医者の診療
書いた人:医者ブラウンホーファー(1825年)
「頭はいかがですか」
「足に痛みや疲れの感覚はありませんね」
「ワイン、コーヒー、スパイスは禁止です。あなたのコックにもそう申し伝えますから」
「朝はチョコレートを、ただしバニラやミルクや水は抜きで。昼は私の指示にしたがってスープを飲んでもよろしい。半熟卵はコショウなしで」
かげはら史帆さん:ベートーヴェンが風邪をこじらせてしまったとき、医者が診察に来て、いろいろやりとりするんですが、その問診の様子がまるごと会話帳に残っています。「これは食べちゃダメ」「こういう治療をしなさい」みたいなことが細かく書かれていて、当時の医療や食事療法がどんなものだったのかリアルに伝わってきます。

●同業者のうわさ話
書いた人:シュパンツィヒ(1823年)
「フィールドの演奏は美しい」
「あの男がベートーヴェンを弾くのは一聴に値するよ」
「彼はレッスンで大もうけしているが、シャンパン代に使っちまって、100フロリンも持っていないんだ」
かげはら史帆さん:会話帳には同業者に関する“うわさ話”もちらほら登場します。映画にも登場するヴァイオリニストのシュパンツィヒが、当時としても有名だったピアニストのジョン・フィールドについて話している記録も残っていて、「フィールドの演奏は素晴らしい!」と褒めたかと思えば、「でもあの人、お酒ばっかり飲んでてお金ないらしいよ」なんて話題も。
●ベートーヴェン本人のメモ書き
書いた人:ベートーヴェン(1825年)
「1825年9月25日。新型の利器、蒸気式コーヒーメーカー。熱い蒸気によってかぐわしい香りを生み出し(……)コーヒーが出来上がるスピードを速めます」
かげはら史帆さん:ベートーヴェン本人がコーヒーメーカーの商品情報をメモ書きしています。おそらく当時の新聞広告を見て、気になった内容を自分で書き写したものと思われます。実は彼はかなりのコーヒー好きで、1杯分のコーヒーに使う豆の数を“きっちり60粒”と決めていたくらいのこだわり派。別の場所のメモ書きにも「コーヒーメーカーを見る」なんて書いてあって……天才作曲家が、真剣にコーヒーメーカーをチェックしていたかもしれないと思うと、なんだかかわいいですよね(笑)。
ただのメモ書きだからこそ見えてくる、200年前のあれこれ

――会話帳を読んでいる中で、「こんなの見ちゃっていいの!?」と驚いた瞬間はありましたか?
かげはら史帆さん:たくさんありますよ(笑)。中には、けっこうな悪口が書かれていたりして「うわ…読んじゃった」ってちょっとショック受けることも。たとえば、ベートーヴェンの秘書だったカール・ホルツは、よく人の悪口を言うんですよ。そういう悪口をベートーヴェンに伝えることで、笑わせたりコミュニケーションをとっていたようなんです。こういうやり取りからも、当時の人間関係やそれぞれの性格が垣間見えきますよね。こんな形で200年後の人にのぞかれるなんて思って誰もなかったはずだからこそ、余計にリアルで、ちょっとドキドキします。
――後世に伝えようとして書かれたものじゃない、偶然残ったただのメモなだけに、そこがまたリアルで面白いですね。
かげはら史帆さん:そうなんです。会話帳って、正式な記録じゃなくて、本当にただのメモ書きなんですよね。たとえば、「+ピケ織りの毛布 +歯ブラシ +帽子」なんていう“ほしいものリスト”まで残っていて。そういうのを見ると、「あ〜ベートーヴェンも歯ブラシ買ってたんだな」って、急に身近に感じられますよね。

――200年前も今も、やってることは案外変わらないんだなって思うと、なんだか親近感が湧いてきますね。では、最後に、映画『ベートーヴェン捏造』の見どころを教えてください。
かげはら史帆さん:映画の中では、ベートーヴェンと周囲の人々が“会話帳”を通してやり取りするシーンがたくさん登場します。内容は観てのお楽しみですが、会話帳が“影の主役”のような存在として物語に深みを与えているので、ぜひ注目してみてください。

* * *
9月12日公開の映画『ベートーヴェン捏造』では、「会話帳」がどんな登場の仕方をするのか…。私たちが知らなかったベートーヴェンの新たな一面に、きっと心を動かされるはずです!
映画『ベートーヴェン捏造 』
【ストーリー】
耳が聞こえないという難病に打ち克ち、歴史に刻まれる数多くの名曲を遺した偉大なる天才音楽家・ベートーヴェン。しかし、実際の彼は――下品で小汚いおじさんだった…!?
世の中に伝わる崇高なイメージを“捏造”したのは、彼の忠実なる秘書・シンドラー。どん底の自分を救ってくれた憧れのベートーヴェンを絶対に守るという使命感から、彼の死後、そのイメージを“下品で小汚いおじさん(真実)”から“聖なる天才音楽家(嘘)”に仕立て上げていく。しかし、そんなシンドラーの姿は周囲に波紋を呼び、「我こそが真実のベートーヴェンを知っている」、という男たちの熾烈な情報戦が勃発!さらにはシンドラーの嘘に気づき始めた若きジャーナリスト・セイヤーも現れ真実を追究しようとする。シンドラーはどうやって真実を嘘で塗り替えたのか?果たしてその嘘はバレるのかバレないのか――?
タイトル:ベートーヴェン捏造
原 作:かげはら史帆『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(河出文庫刊)
主 演:山田裕貴
出 演:古田新太、染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、野間口徹、遠藤憲一 ほか
脚 本:バカリズム
公 開:2025年9月12日
(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd. All Rights Reserved.
取材・文=宇都宮薫
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」
気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細