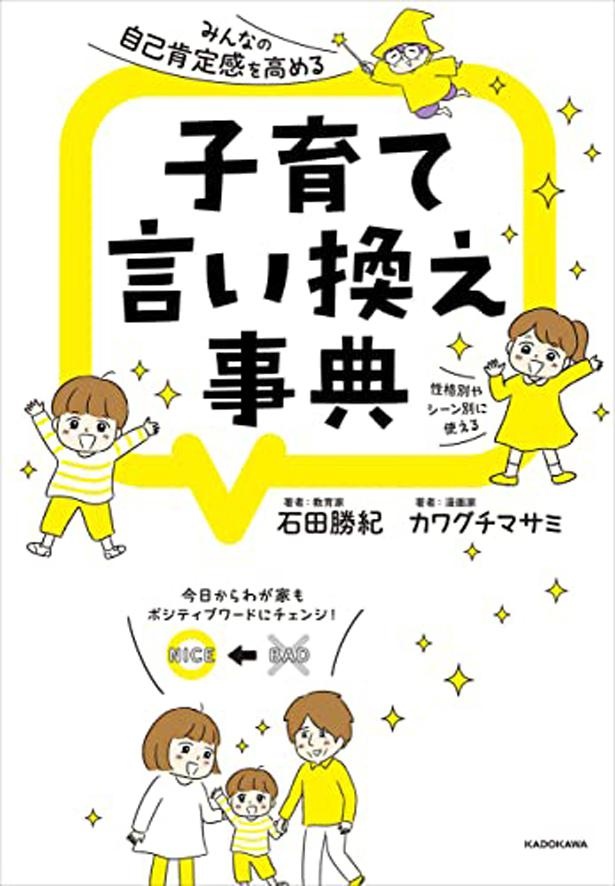子どもの自己肯定感を高めるための会話法、そのポイントは「質問」すること!/子育て言い換え事典(6)
宿題をやっていないのに「やった」とウソをつく子へ

ボキャブラリーの少なさや認識違いで「ウソをついたように見える」ことも
子どものウソに対する声かけは、その内容や子どもの気質によって変わるため一概にはいえません。ただ、子どもがあきらかにウソをついたと思うような場面でも、よくよく話を聞いてみると、“親と子どもの認識に相違があるだけ”ということがあります。
たとえば親が「宿題はやった?」と質問し、子どもが「やったよ」と答えた場合。親は「宿題をやる=宿題がすべて完了した状態」と認識し、子どもは「宿題をやる=1問解いた状態」と認識していたとしたら、当然ながらすれ違います。子どもはウソをついたつもりがありませんから、親に疑われたと傷つき、反発するでしょう。
もしも子どもが宿題を一切やっておらず、まったくのウソだった場合。「たいしたことではない」とスルーする選択肢もあります。ただ、子どもに「ウソはダメ」と伝えたいと思ったとき。諭したり、忠告したりする際のポイントは「さらっとひと言だけ」です。「やっていないならやっていないって言っていいよ」「正直に言っていいんだよ」などと伝え、しつこく繰り返さないようにします。
ウソがばれた時点で子どもは内心「ウソをついた自分が悪い」とわかっています。しかし、しつこく言われることで「しつこく注意してくる親がうるさい」と論点をすりかえてしまうのです。子どもの心に響かせるためにも、短くひと言で、終わらせるようにしてみてください。
育児への向き合い方
ウソだと決めつける
のではなく、
↓
お互いの認識を確認する
に思考チェンジ!
自己肯定感を高めるワンポイント
ウソにもいろいろな種類があります。たとえば人を助けるためのウソは一般的には「ダメなもの」とされません。どのウソをどこまで許容するかは家庭ごとの判断になりますが、よかれと思ってついたウソや、自分自身がウソだと認識していないことで責められるのは、子どもにとってつらいことです。また、親が子どもを疑うことは、親子の信頼関係に少なくない影響を与えます。
ポイント
子どもがウソをついているかもと思ったら、まずは慎重に見極める
著=石田 勝紀、カワグチ マサミ/『みんなの自己肯定感を高める 子育て言い換え事典』(KADOKAWA)
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」
Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
コミックエッセイランキング
コミックエッセイをもっと見る
作品を検索する
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細