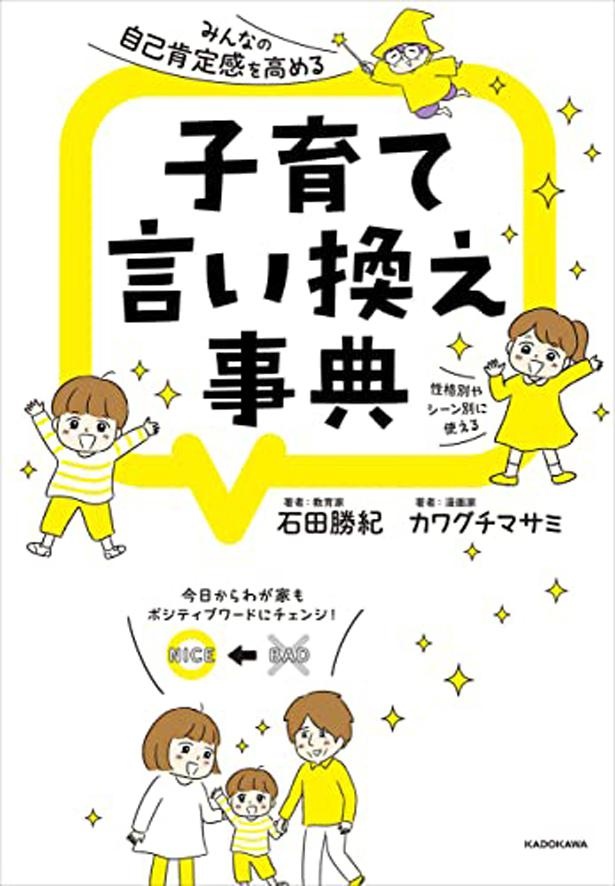「この宿題、むずかしい!」問題が解けずにかんしゃくを起こす子どもへかける言葉は?/子育て言い換え事典(11)

「ゲームや動画に夢中になってしまう」「口答えや言い訳ばかり言う」「宿題を解くのに時間がかかる」…子どもたちがこんな状況の時、どのような声かけをしていますか?
親の言葉が知らず知らずのうちに子どもの心を傷つけ、自己肯定感を下げてしまっていることがあります。ついつい言ってしまいがちが「ネガティブワード」を、どのような「ポジティブワード」に言い換えればいいのでしょうか。
これまで5万人以上の生徒を指導し、全国で保護者の相談に応えてきた教育専門家の石田勝紀氏が、実際に行ってきたアドバイスとその成果をもとに、子どもへの適切な声かけを「場面別」「性格別」にわかりやすくまとめました。
ご自身も育児に奮闘中の漫画家・カワグチマサミさんのイラストで、子どもの自己肯定感を高める言葉の選び方をご紹介します!
※本作品は石田 勝紀、カワグチ マサミ著の書籍『みんなの自己肯定感を高める 子育て言い換え事典』から一部抜粋・編集しました。
「この宿題、むずかしい!」問題が解けずにかんしゃくを起こす子どもへ

かんしゃくを起こす子は、怒っているのではなく、困っている
宿題や勉強が思うようにできなくて、子どもがかんしゃくを起こしたとします。
子どもが怒ると、親は心がかき乱されて、つられて怒ってしまったり、なだめるような声かけをしたりしてしまいがちです。しかし、親が感情的になればなるほど、子のかんしゃくは悪化するもの。そもそもの原因に目を向け、課題解決のサポート役に徹したほうがいいでしょう。
勉強で困っていたら、「どこまでできたのか、教えて?」と近づきます。「ここまではできた」という箇所がわかれば、どの部分でつまずいているかがわかるからです。そして、つまずいている部分の解き方だけを教えて、「あとは、自分でやってみて」とその場を離れます。
よくあるのが、子どもの隣りに座り、最初から最後までつきっきりで教えようとすること。「これは、こういうふうに解くんだよ」と答えまで教えてしまうのはオススメしません。その方法では子どもの自立心は育ちませんし、なによりその子が「自分で解けた!」という感覚を得られないからです。つきっきりで教えると、意欲的ではない子どもに腹を立て、親子ゲンカに発展してしまう可能性も。
自力では困難な部分だけをサポートする。子どもが「自分でできた!」と感じられるような余地を残す。これが、子の成長を支援するときのコツです。
育児への向き合い方
最後まで教える
のではなく、
↓
自力でやる余地を残す
に思考チェンジ!
自己肯定感を高めるワンポイント
たとえば小さなお子さんが「靴を自分で履きたいけれど、履けない!」というとき。親はまず、自力でやるのが難しいのは、どの部分なのかを観察します。そして「ここだけお手伝いさせてね」と、たとえばつま先だけを入れてあげるなど部分的にサポート。すべてを手伝おうとせず、自分でやれる作業を残すことが大切です。すると子どもは「自分で履けた!」と思い、自立心や挑戦する心が育ちます。
ポイント
つまずいているポイントはどこ?まずは観察してみよう
著=石田 勝紀、カワグチ マサミ/『みんなの自己肯定感を高める 子育て言い換え事典』(KADOKAWA)
Information
おすすめ読みもの(PR)
コミックエッセイランキング
-
 1位
1位そのまま帰らぬ人となった妻…ベッドから落ちたまま起き上がってこなかった朝/私がシングルファザーになった日(1)
-
 2位
2位平穏な日常が続くと思っていた。誰が息子の心を壊したの?/性被害のせいで、息子が不登校になりました(1)
-
 3位
3位夫のスマホに届く不倫相手からのメッセージ。でも「私は幸せだ」と自分に言い聞かせて/私はあのママ友より幸せだと思っていたのに(1)
-
 4位
4位「お姉ちゃん、いじめられてるんだって」。見つけた「娘の写真」に母はショックを…/家族全員でいじめと戦うということ。(1)
-
 5位
5位担当した浮気マンガが大ヒットした編集者。今度は自分が「サレ妻」になるなんて…/探偵をつけて浮気に完全勝利する(1)
コミックエッセイをもっと見る
作品を検索する
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細