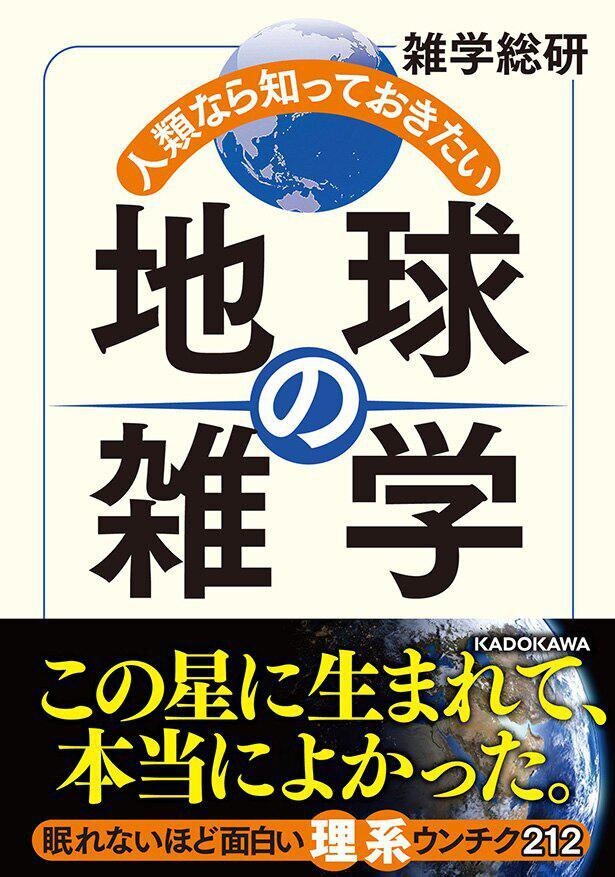乾電池の発明者は「日本の時計職人」だった!? 知られざる発明のきっかけ/人類なら知っておきたい 地球の雑学(94)

あらためて考えると、この地球(ほし)にまつわるさまざまなことは「知っているようで知らない」ことが多いのではないでしょうか…。
太陽系を含む地球の歴史をはじめ、地球上で成立した大自然や気候、動植物、資源など、地球に生きる私たちが知っておくべき「理系雑学」をお届けします。
思わず誰かに話したくなる理系ウンチクは、職場や家庭での日々の雑談に役立つかもしれません!
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
乾電池の発明者は「日本の時計職人」!?作ったきっかけとは?
電池は、のちに電圧の単位「ボルト」の語源になった、イタリアの物理学者ボルタによって1800年頃に発明された。ボルタが発明したボルタ電池は、銅と亜鉛を食塩水や希硫酸に浸したものだったが、その約35年後、イギリス人のダニエルがボルタ電池の欠点を改良したダニエル電池を発明。さらに1867年には、フランス人ルクランシェが、今の乾電池と同じく二酸化マンガンを使った電池を発明した。
だが、いずれの電池も溶液がこぼれるなどの難点があった。
そこで1888年、ドイツのガスナーらが、液のこぼれない電池、いわゆる乾電池を発明し、その特許を申請。そのため、世界ではガスナーらが電池の発明者とされている。しかし、それに先立つこと1年、1887年の時点で、日本人の屋井先蔵(やいさきぞう)の手によって乾電池が発明されていたことは、あまり知られていない。
屋井は、長岡藩(現在の新潟県)の出身で、東京で時計職人として働いていた。そして1885年、「連続電池時計」の発明に成功したが、時計に使用していた輸入電池には、薬品が染み出して金具が腐食するなどの欠点があった。そこでみずから発明したのが「屋井乾電池」だった。
1892年には、東京帝国大学理学部がシカゴ万博に出品した地震計に屋井乾電池が使用されていたことから、世界的に注目を浴びる。ところが、権利関係の知識にうとかった屋井が、みずからの発明した乾電池の特許を出願したのはその翌年のこと。この頃にはすでに、屋井乾電池の模造品がアメリカから逆輸入されていたという点からも、その優れた性能が証明されているといえるだろう。
著=雑学総研/『人類なら知っておきたい 地球の雑学』
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「ノザキのコンビーフ(80g×6 個)」」
そのままでも調理してもおいしいから、ローリングストックに最適!
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細