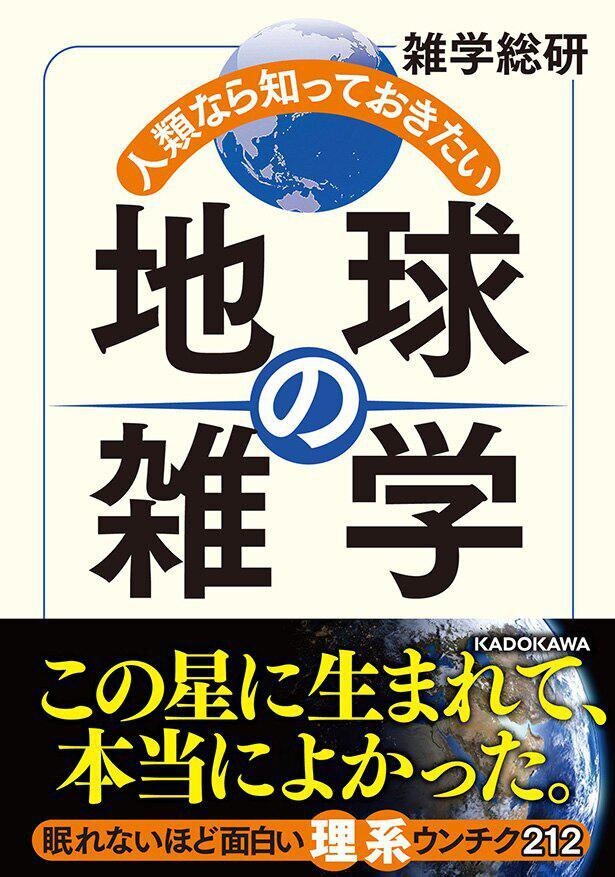なぜ秋になると葉っぱは赤や黄色に色づくのか?その真相とは/人類なら知っておきたい 地球の雑学(120)

あらためて考えると、この地球(ほし)にまつわるさまざまなことは「知っているようで知らない」ことが多いのではないでしょうか…。
太陽系を含む地球の歴史をはじめ、地球上で成立した大自然や気候、動植物、資源など、地球に生きる私たちが知っておくべき「理系雑学」をお届けします。
思わず誰かに話したくなる理系ウンチクは、職場や家庭での日々の雑談に役立つかもしれません!
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
なぜ秋になると葉っぱは赤や黄色に色づくのか?
秋になると、木々が赤や黄色に色づき、美しい光景を楽しめる。どういうしくみで、緑の木の葉があのように色を変えるのだろうか。
赤になる葉と黄色になる葉では、メカニズムが違う。まず、木の葉が緑色をしているのはクロロフィルという緑の色素があるからで、気温が低くなるとこの色素は分解される。
違いが出るのはここからだ。黄色になる葉はもともとカロテノイドという黄色の色素も持っているが、緑の色素のほうがずっと多いので緑に見えていた。それが、気温が低くなると緑の色素が壊れてカロテノイドが目立つようになり、黄色くなるのである。
赤くなる葉も緑の色素が壊れるのは同じだが、葉にたまった糖などからアントシアニンという赤い色素が新しくでき、そのため赤く見えるようになっている。気温が下がると落葉の準備が始まり、葉と枝のあいだに離層ができる。そのため葉の光合成でできた水や養分の行き来が止まって糖が葉にたまり、たくさんのアントシアニンの合成が始まるのである。黄色くなる葉のほうは、この赤い色素をつくるしくみを持っていないと考えられている。
木の葉は最低気温が8℃以下になると色づき始め、5~6℃になると急に色が変わるという。しかし、植物が何のために色を変えるのかは、よくわかっていない。鳥に果実がなっていることをアピールするため、紫外線から身を守るためなど、さまざまに考えられてはいるが、真相はいまだ謎なのだ。
また、晴天が続いて昼夜の寒暖の差が大きい年にはよりあざやかな色になるが、これも理由は不明である。
著=雑学総研/『人類なら知っておきたい 地球の雑学』
Information
おすすめ読みもの(PR)
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細