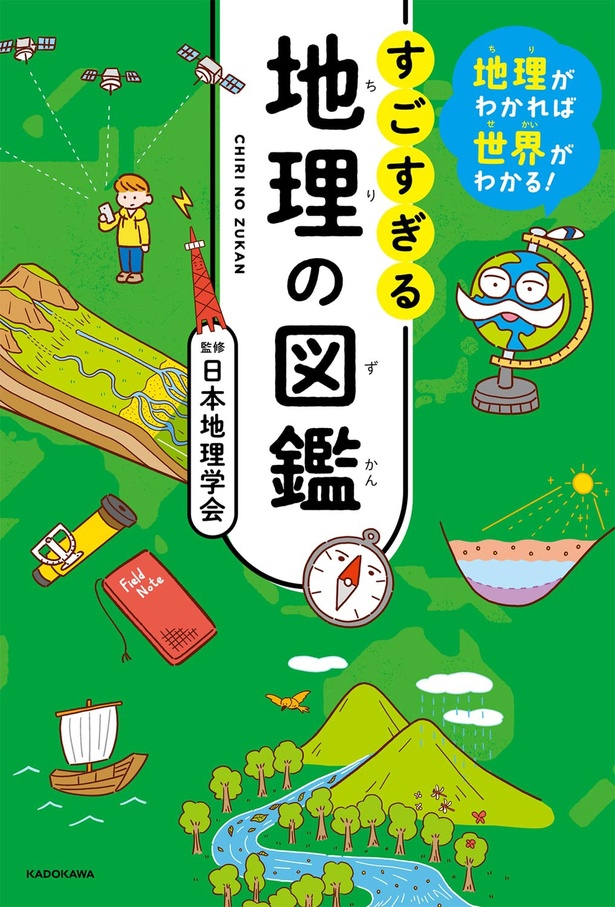地図界のレジェンド伊能忠敬。正確な日本地図を作ったのは壮大な夢のためだった!/すごすぎる地理の図鑑(8)

普段ニュースで見聞きする政治や経済、観光地にグルメ。実はこうした様々な情報がすべて「地理」につながっているって、知っていましたか? 地理の勉強は、地名を暗記したり地図を眺めるだけじゃないんです!
地図からわかる地域の自然環境や歴史、暮らしぶりなどは、地理を学ぶとその背景や理由、意外な事実が見えてきて、ぐっと理解が深まります。地理は「地域の謎を解くカギ」と言える、とても身近で面白い学問なのです。
世界のことが今よりもっとわかるようになる、地理のネタあれこれをお届けします。
※記事の情報は2023年3月現在のものです。
※本記事は日本地理学会著の書籍『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』から一部抜粋・編集しました。
伊能忠敬が地図をつくった本当の目的
江戸時代に地図をつくったことで知られる伊能忠敬は、現在の千葉県の商家の主でした。50歳で息子に家業をゆずり、その後幕府天文方に弟子入りしました。
天文学や測量術を学ぶうちに、彼は地球の大きさを測りたくなりました。そのためには、距離を正確に計測する必要があります。そこで海岸線を歩いて測量を行い、正確な地図を作成し、南北の距離を算出しました。忠敬にとって、地図作成は地球の大きさを測定するための手段だったのです。
1800年、55歳の忠敬は、私財をなげうち、蝦夷地(現在の北海道以北)に向けて第1次測量に出発しました。その計測で得られた地球の大きさは、現在計測されている値との差がわずか0.2%程度。また、作成された地図の精度は幕府も驚くほど高く、のちに幕府の正式な事業となりました。忠敬と弟子がつくり上げた「大日本沿海輿地全図」( 伊能図)は、明治中頃まで日本政府の正式な地図のもととして使われました。
伊能忠敬は強靭な精神力の持ち主
伊能測量隊の測量方法
ある地点から次の地点を見通してその方向を計測し、また歩測や縄を使って距離を測定することを延々と続けることで、一筆書きの測量線を引いていく。さらに夜は天文観測を行って緯度を求めた。忠敬の測量結果が正確だったのは、とにかく几帳面にこつこつと測量を続けた結果なのだ。
1歩が69cmになるよう徹底的に訓練

伊能忠敬像(富岡八幡宮/東京都江東区)
忠敬は測量旅行の出発の度に、富岡八幡宮を参詣して成功を祈願したとされる。


伊能中図の「関東」図(模写)
1874(明治7)年以降に、陸軍省参謀局により模写された「関東」図。陸軍が頼ったのも伊能忠敬の地図だったのだ。
豆知識
日英修好通商条約(1858年)による開港で、日本沿岸の測量を考えたイギリスは、1861年に測量船を日本へ派遣。その際に幕府から提供された伊能図の精度の高さに驚き、測量の必要はないと判断して帰国しました。
著=日本地理学会/『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」
気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細