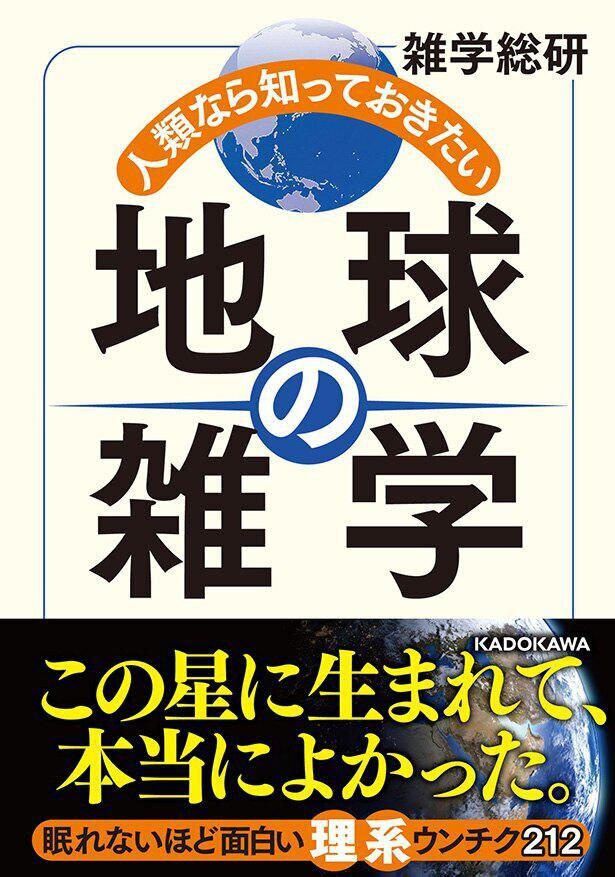空から降ってくる雨粒のカタチは?じつは「しずく型」ではない!

地球上で起きていること、どれだけ知っている?
この地球で当たり前に感じていることでも、うまく説明できないことがありますよね。例えば、「青い空が夕暮れに赤く染まるのはなぜ?」「台風が日本列島めがけてやってくる理由は?」
そんな地球に生きる私たちが知っておくべき「理系雑学」をご紹介します。太陽系を含む地球の歴史をはじめ、地球上で成立した大自然や気候、動植物、資源など、地球をめぐる大疑問にスッキリ回答!あらためて考えると、私たちはこの地球にまつわるさまざまなことを、じつはほとんど知らないのかもしれないかもしれません。
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
雨粒は、決して「しずく型」ではなかった⁉
雨粒のイラストは、上部がとがった「しずく型」になっているのがお決まり。でも、雨粒は本当にそんな形をしているのだろうか。
雲の中にあるとき、雨粒はまだ小さく、表面張力の働きでボールのような球形をしている。それが次第に大きくなったり、雨粒同士くっつくことで重くなって落ちてくる。気象庁の定義では、直径0.5ミリメートル未満のものが霧雨で、0.5ミリメートル以上になると雨なのだが、このときもまだ球形である。
だが2ミリメートルほどの大きさになると、下から空気抵抗を受けるので、下のほうが平たくなる。上半分は丸くて下半分はぺちゃんとつぶれた、おまんじゅうのような形である。さらに、7ミリメートルくらいに大きくなったり、落ちるスピードが速くなったりすると、おまんじゅうのような形の雨粒は、割れて小さな粒になる。
このように、空から降ってくる雨粒は、球形または水平につぶれた形で、しずく型になることはないのだ。
では、なぜしずく型が雨粒のイメージとして定着したのか。低いところから落ちる水滴は空気抵抗をさほど受けないので、しずく型をしていることがある。雨粒も、いったん木に降ってそれから落ちてきたり、窓ガラスを伝っているときは、しずく型になる。それを見て、雨はしずく型だと考えられたのだろう。
また、雨粒はどんなに大粒に感じても、1センチメートルを超えるものはない。落ちてくるスピードも、雨粒が大きいほど速いのだが、7ミリメートルほどになると割れて小さな粒になるので、どんなに速くても秒速10メートル程度である。
著=雑学総研/『人類なら知っておきたい 地球の雑学』
Information
おすすめ読みもの(PR)
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細