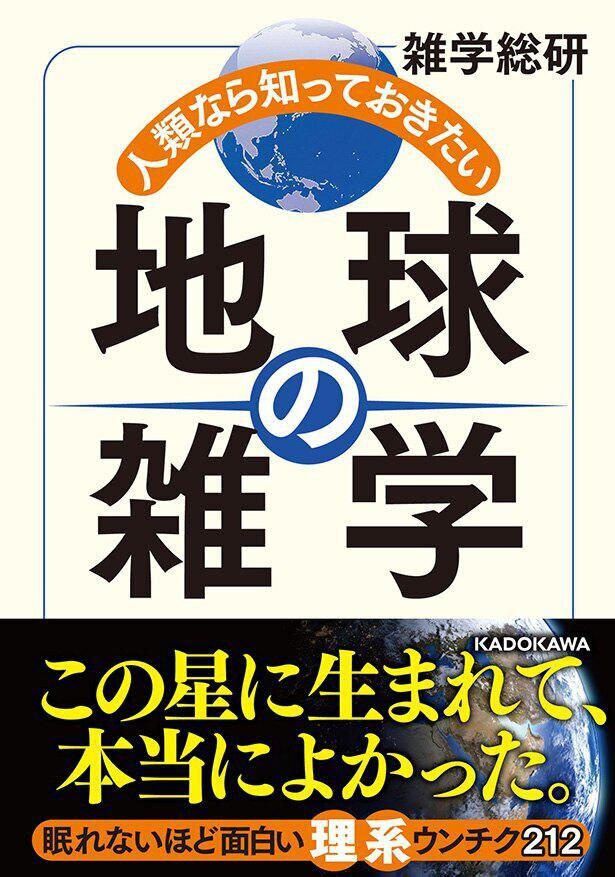「切り株の年輪を見れば方角がわかる」はウソ!?うっかり信じてしまうと危険!

地球上で起きていること、どれだけ知っている?
この地球で当たり前に感じていることでも、うまく説明できないことがありますよね。例えば、「青い空が夕暮れに赤く染まるのはなぜ?」「台風が日本列島めがけてやってくる理由は?」
そんな地球に生きる私たちが知っておくべき「理系雑学」をご紹介します。太陽系を含む地球の歴史をはじめ、地球上で成立した大自然や気候、動植物、資源など、地球をめぐる大疑問にスッキリ回答!あらためて考えると、私たちはこの地球にまつわるさまざまなことを、じつはほとんど知らないのかもしれないかもしれません。
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
「切り株の年輪を見れば方角がわかる」はウソだった⁉
木の幹の内部にある「年輪」には、木が生きてきた歴史が刻まれている。年輪は、樹皮の下にある形成層という部分が、木の幹を内側に押し込みながら、外側に向かって成長していく過程でできる。その期間が1年に1回であることから、年輪を数えれば樹齢を知ることができるというわけだ。
山や森に入って道に迷ってしまったとき、「切り株の年輪を見れば方角がわかる」とよくいわれる。樹木は日の当たる南側のほうががよく成長することから、年輪の幅が広いほうが南になる、という寸法だ。しかし、この説をうっかり信じてしまうと遭難する可能性があるので、注意しなければならない。
確かに年輪の幅は一定ではなく、狭いところもあれば広いところもあり、広いほど成長がよかったことを表している。ただし、日の当たる方角の年輪だけが広くなるわけではない。立地条件によっても年輪の幅は変化するのだ。
たとえば、斜面に生えている樹木の場合、幹が傾かないようバランスをとるため、年輪の幅に差が出ることがある。さらに、木の種類によっても、バランスのとり方が異なっている。針葉樹の場合、幹を斜面から出っ張らせ、樹木全体を押し上げるような形でバランスをとって成長しようとすることから、谷側の年輪の幅が広くなる。反対に広葉樹は、樹木全体を上に引っ張り上げるような形で、斜面に平行しながら成長しようとすることから、山側の幅が広くなるのだ。
ちなみに、年輪ができるのは、日本のように季節の違いがはっきりしている地域の樹木にかぎられている。合板(ベニヤ板)に使われるラワンのように、熱帯に育つ樹木には年輪ができないという。
著=雑学総研/『人類なら知っておきたい 地球の雑学』
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「記事を読んでアンケートに答えるとQUOカード1,000円分が3…」
夏休みに親子で学ぼう!電気とエネルギーの話
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細