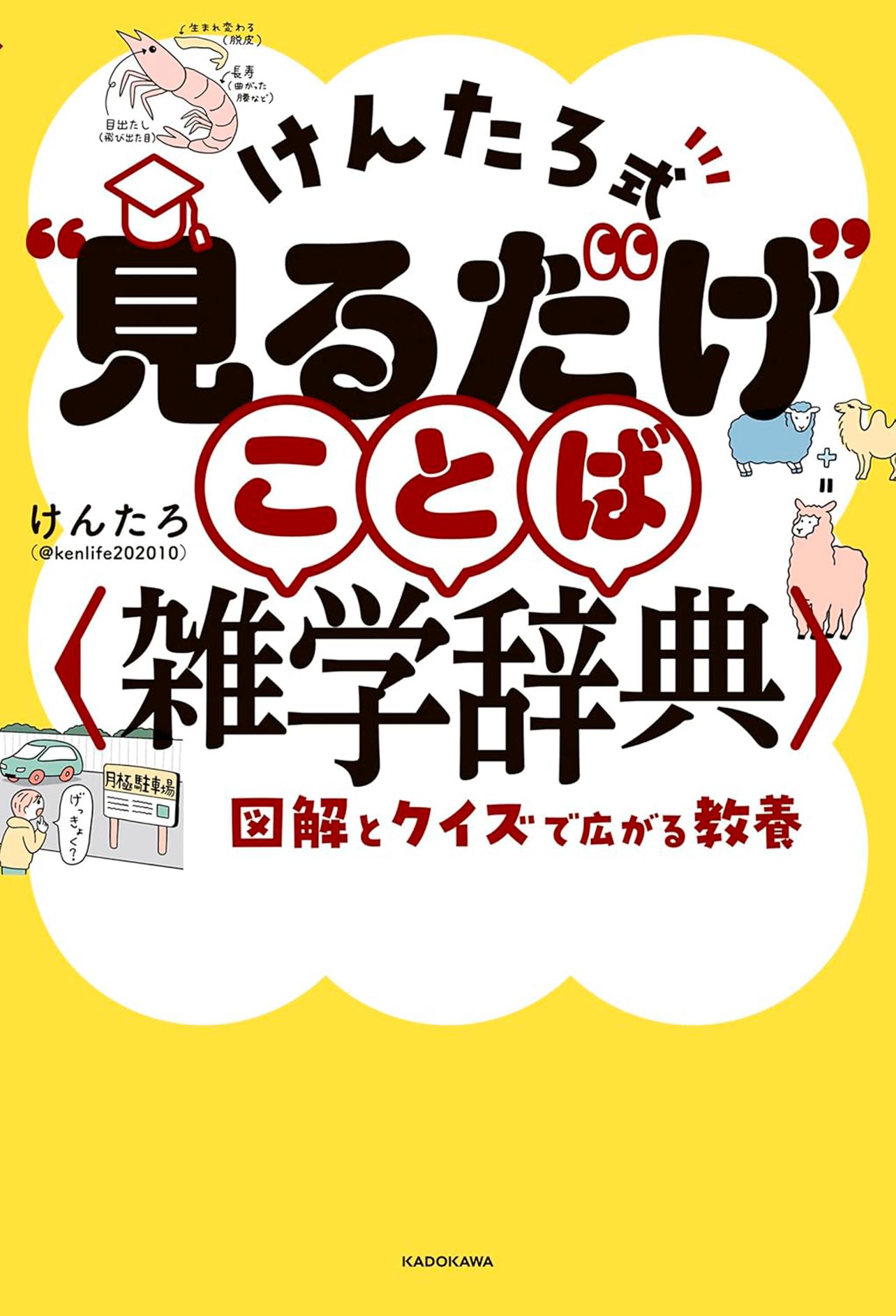-
1
- 2
「竜髭菜」「芽花椰菜」はなんと読む?読めたらすごい野菜・果物の漢字36選

日常で使ったり耳にしたりする言葉の中には、実は意味を間違えて使っているものが意外にたくさんあったりします。例えば、「さわり」という言葉を「話の冒頭部分」と思っている人が多いですが、本来は「話の要点」を指します。
こうした身近な言葉にまつわる常識や雑学を、人気インフルエンサーのけんたろさんが分かりやすくまとめた図表が、「見るだけで覚えられる!」とXで大好評! 本記事では、誤解されやすい言葉、知っていると一目置かれる難読漢字、知っているようで知らない身近なモノの正式名称などを図表と解説で紹介します。
「なるほど、そうだったのか!」という発見や驚きを通して、言葉の知識が楽しく広がり深まります!
※本記事はけんたろ著の書籍『けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養』から一部抜粋・編集しました。
野菜・果物の難読漢字

野菜・果物の名前も、普段はひらがなやカタカナで見かけることが多いです。語源などもまとめましたので、ぜひ、読みと併せて漢字の成り立ちを想像しながら読んでみてください。
胡瓜
キュウリ。「胡瓜」という漢字は中国語由来ですが、昔は「黄瓜」と書かれていました。というのもキュウリは熟すと黄色になるからです。私たちが普段食べている緑色のキュウリは、実が熟していない状態のものです。昔は黄色くなるまで完熟させて食べられていました。一方中国では、「胡」の字が異民族を表し、差別語と捉えられた時代があり、現在では「黄瓜」と書くそうです。
蜜柑
ミカン。中国から渡来した当時は「柑子(かんじ )」と呼ばれていました。室町時代になり、糖度が増した品種が作られたことで、「蜜のような甘さの柑子」と評判となり「蜜柑」という名前になりました。
南瓜
カボチャ。カンボジア原産と考えられ、その国名にちなんで「カボチャ」と呼ばれました。漢字はカボチャの中国名によるものです。
葡萄
ブドウ。原産地は古代ペルシアと言われ、ギリシャ語で“botrus”と呼ばれていたものが中国に伝わり、発音から似た音の「葡萄」の漢字が当てられました。日本では古くは山ぶどうなど自生していたものを「えびかづら」と呼んでいました。理由は山ぶどうのつるが海老のひげのように巻いていることと、つる草の総称を「かづら」と呼んでいたためです。
玉葱
タマネギ。ペルシャ原産で明治になり日本にやって来ました。従来の「長ネギ」と違って球状になることから「玉ネギ」と名付けられました。
柚子
ユズ。「子」には果実という意味があり、中国由来の読み方で「ズ」と発音します。「杏子(あんず) 」も同じ例です。
茄子
ナス。名前の由来は、昔の「なすび」は酸っぱい味だったため、「中が酸っぱい実」から「なかすみ」⇒「なすみ」⇒「なすび」と変化しました。「び」が脱落した理由としては、江戸の商人が縁起のよいものとして「なすび」を売ろうと考えた時に、成功を意味する「成す」とかけて「なす」として販売しそれが広まりました。
蕪
カブ。根の丸い形状から「頭(かぶ)」に由来するとされています。元は「かぶら」であり、そこから女房詞の「おかぶ」を経て「かぶ」となったとされます。ちなみに春の七草のスズナはカブのことです。
枇杷
ビワ。楽器の琵琶に似ているため名付けられたとされますが、どう似ているのかはっきりはしていません。漢字から元々は「ビハ」と発音されていましたが、次第に「ビワ」となりました。
山葵
ワサビ。その辛みから「悪障疼(わるさはりひびく)」の略という説があります。葉の形が葵の葉とよく似ていて、山の中の清流に生えることから「山葵」と書くようになりました。
酢橘
スダチ。「酸っぱい橘」が語源。スタチが濁音化してスダチとなりました。同じような語源を持つ語に、「酸っぱい桃」からの「スモモ(李・酢桃)」があります。
茗荷
ミョウガ。よく物忘れの代名詞になっていますが、ミョウガを食べたからといって物忘れがひどくなるわけではありません。これは釈迦の故事に由来します。釈迦の弟子に物忘れのひどい者がおり、首から名荷(名札のこと)をかけさせましたが、その存在さえも忘れてしまい亡くなりました。そんな彼の墓から生えたのがミョウガとされています。
糸瓜
ヘチマ。漢語の糸瓜を「イトウリ」と訓読みし、「トウリ」に訛りました。トはイロハのヘとチの間にあることから「ヘチマ」になったという説があります。
西瓜
スイカ。熱帯アフリカ原産で、西から伝わり瓜に似ていたことからこの漢字が使われるようになりました。スイカの語源は漢字の中国由来の読み方「スイクワ」に由来します。水分が多いことから「水瓜」という漢字も使われます。
木耳
キクラゲ。味がクラゲに似ていて、木の上にあることから名付けられたとされます。漢字は形状が耳の形に似ていることに由来します。
胡桃
クルミ。「胡」は中国人から見て「西の方に住む異民族」を表す漢字です。紀元前2世紀ごろに、シルクロードを探検した中国の武将が西の方から持ち帰ってきたという伝説があります。
萵苣
レタス。「牛乳」という意味のラテン語に由来します。和名では「ちしゃ」と言います。これは「乳草(ちちくさ)」に由来し、レタスも乳草も同じような語源理由です。その理由は、レタスを切ると白い汁が出るためです。
蕃茄
トマト。メキシコの先住民の言語であるナワトル語で「膨らんだ果実」を意味する「トマトゥル」から来ています。漢字は漢名由来で、「蕃」は未開の地や外国という意味があり、トマトはナス科の野菜であることから、「外国から来た茄子」を表しています。このほかにも、「赤茄子」などとも書きます。
Information
おすすめ読みもの(PR)
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細