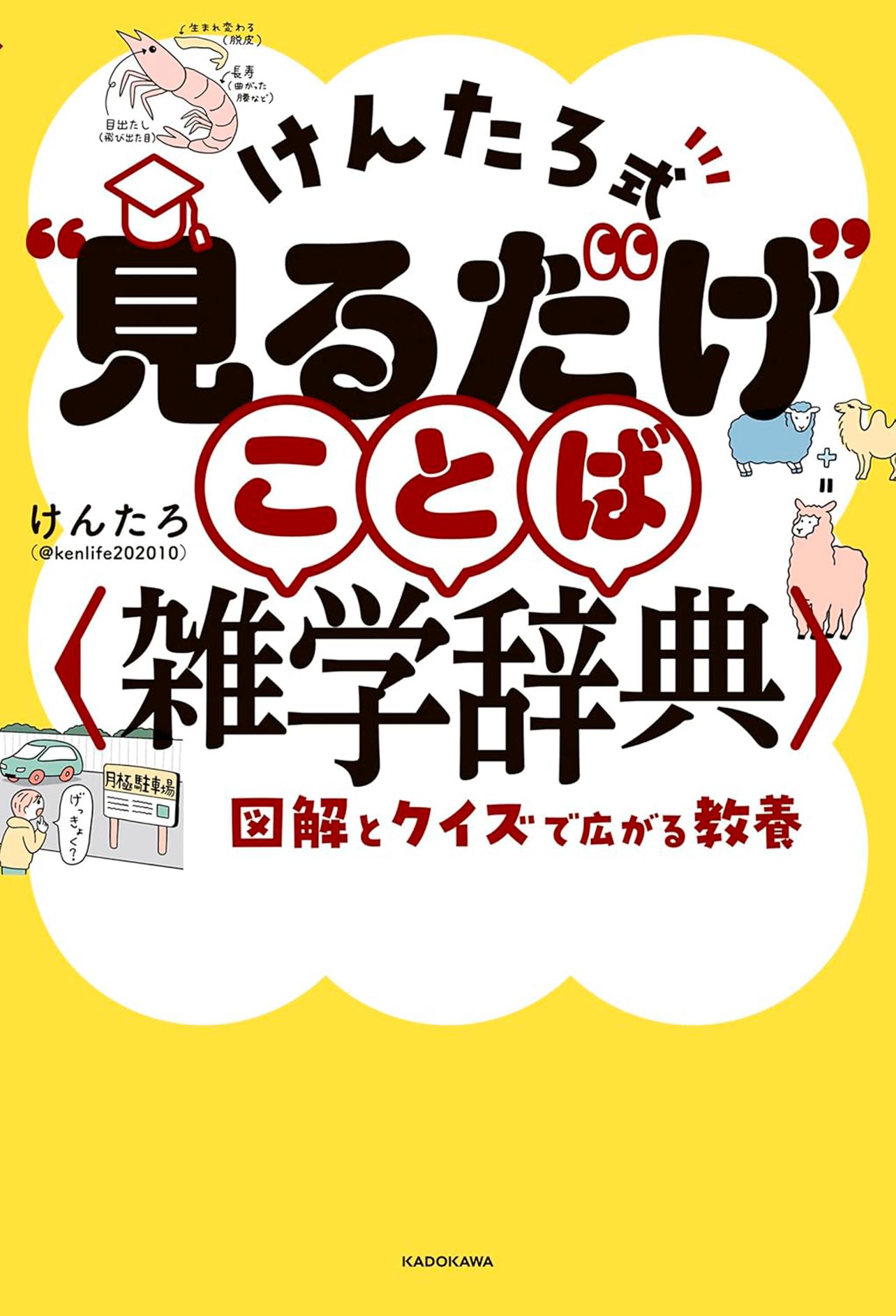- 1
-
2
福引で使うガラガラ、刺身の下に敷く紙… SNSで話題!そういえば呼び名を知らないもの
目打ち
切手シートを購入すると切手と切手の間に施されている小さな穴。切手を一枚ずつ切り離しやすくするために開けられています。そのため一枚一枚の切手は端がギザギザになっています。「目打ち」の由来は紙に穴を開けることおよびその道具のことを昔から「目打ち」と呼んでいたことからです。1871年に発行された日本初の切手である竜文切手にはこの穴はなく、1872年に発行された竜銭切手から採用されました。ちなみに、切手シートの余白の部分を「耳紙(みみがみ)」と言います。
魚尾(ぎょび)
原稿用紙の真ん中にある蝶ネクタイのような印。魚の尾の形に似ていることから「魚尾」と名付けられています。原稿用紙をちょうど真ん中で折れるようにするための印です。江戸時代の頃からあったそうで、袋綴じの和本や、製本作業に役立っていたようです。
雷紋(らいもん)
ラーメンの丼の内側をぐるっと一周縁取っている渦巻き模様。古代中国からある伝統的な模様で、魔除けなどの意味を持ち、雷を表しているという説から「雷紋」と呼ばれています。雷は豊作をもたらすものとされ、実際に肥料の三要素の1つである窒素が、大量の電流により大気中から土壌に固着すると考えられ、「稲妻」などの言葉にもそれが反映されています。
擬宝珠(ぎぼし)
橋の欄干の柱頭にあるたまねぎの花のような形をした飾り。五重塔などの仏塔の先端にも同じようなものがありますが、アレは「宝珠」と言います。これに似せて作られたということで、「“擬”宝珠」という名前になったという説と、その昔ネギには厄除けの力があるとされ、玉ねぎの花の形を模して作った「葱帽子」に後からつけられた当て字とする説があります。
絹糸(けんし)
単に「とうもろこしのひげ」と呼んでいますが、実はとうもろこしのめしべです。花粉が絹糸につくと受精します。絹糸はとうもろこしの粒一つ一つに対応しているため、とうもろこしの粒とひげの数は同じになります。その数は品種にもよりますが約600粒(本)。名前の由来は糸のように細く、絹のようにツヤがあることからです。
トグル
冬に着るダッフルコートの前を閉じるためにボタン代わりに付けられている、木製の紡錘形や水牛の爪の形の留め具。英語で「留め木」という意味を持つ「トグル」という名前があります。ボタンと違って手袋をしていても留めやすいメリットがあります。ダッフルコートは第二次世界大戦でイギリス海軍が軍用に採用したことから広がりました。
ボラード
元々は港にあるなぜか片足を載せたくなる、船を係留するためにロープを結ぶものの名前でもあります。これは船をつなぎ止める役割だけではなく、車両を進入させない役割も持っていたため歩道のアレの名前にも使われました。
グレービーボート
グレービーは「肉汁」という意味で、ローストビーフなどにかける「グレービーソース」から来ています。また形状が船に似ていることから「ボート」の名前が付いています。カレーはインドのイメージが強いと思いますが、日本にカレーが伝わったのはイギリスからで、その際にソースを入れる容器として一緒に伝わったものとされます。
アグレット
ひもをほつれづらくして、穴に通しやすくしています。名前はフランス語の“aiguillette” に由来し、「針」を意味します。現代ではほとんどプラスチックで作られていますが、昔は金属や石などで作られていたそうです。ちなみに、アグレットを通す靴の穴のことを「鳩目」と言います。
けんたろ
国公立大学院卒業後、営業マンとして社会人生活をスタート。趣味のクイズや読書を通じて言葉の奥深さを実感。「昨日よりちょっぴり賢いあなたへ」をモットーに、会話が苦手な方の話のネタや、勉強が苦手な方の興味を引く言葉の知識やクイズを発信中。Xフォロワー8.7万人(2024年11月時点)、メディア紹介多数。Voicyパーソナリティとしても活動。
文=けんたろ/『けんたろ式“見るだけ”ことば雑学辞典 図解とクイズで広がる教養』
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「アルジタル デリケートハイジーンソープ」」
刺激に弱いデリケートエリアをやさしく洗う、オーガニックソープ
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細