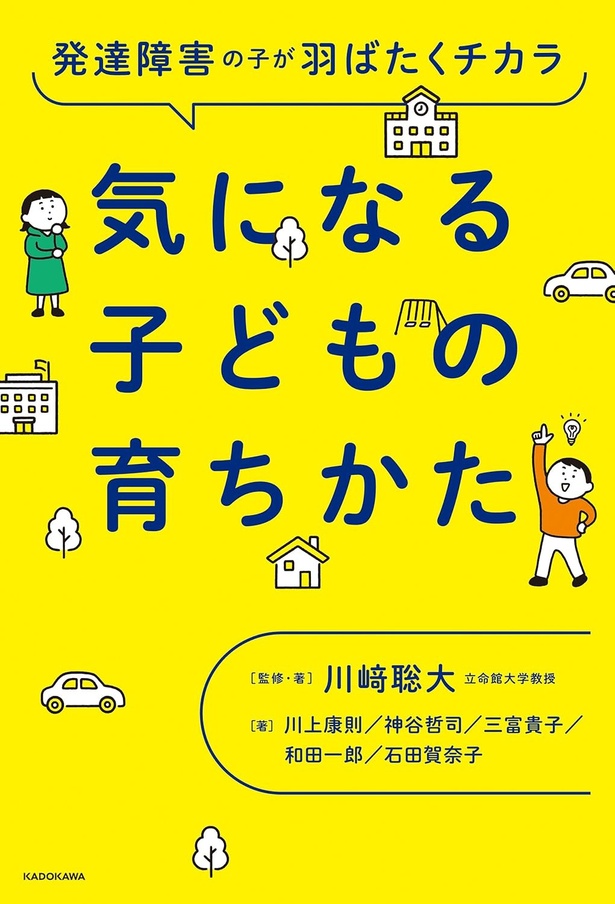概念はそれぞれ違う? 子どもの発達に不安や疑問を感じたときは
発達障害についての認知はかなり進んできましたが、まだ誤解があるのも事実。もし自分の子どもが発達障害だと診断をされたら…どうすればよいか、迷い悩んでしまうことも多いでしょう。
発達障害に関する研究と実践に従事してきた川崎聡大氏(立命館大学教授)が監修し、それぞれの専門家が家庭・学校・地域社会といった育児に必要な全角度から「発達障害の子が幸せに生きていくにはどうしたらいいのか」という視点を提示する本『発達障害の子が羽ばたくチカラ 気になる子どもの育ち方』(KADOKAWA)のなかに、冒頭の疑問を解くカギが記されています。
※本記事は川崎 聡大(監修、著)、川上 康則、神谷 哲司、三富 貴子、和田 一郎、石田 賀奈子(著)の書籍『発達障害の子が羽ばたくチカラ 気になる子どもの育ちかた』から一部抜粋・編集しました。

人々が「発達障害」と言うとき、その概念はそれぞれ違う
「発達障害」というのは、近年急速に広がった概念です。ただ情報の拡散とともに、誤解や偏見も生じて広がっていきます。同じ「発達障害」という言葉を使っていても、話し手の内容と聞き手の理解が同じではないことに、まず注意が必要です。
発達障害の特性は目に見えるものではありません。専門家によるちゃんとした診断は、社会生活を送るうえで困難なことがあって初めて出されるのです。たとえ特性があったとしても、困っていなければ診断されません。
要するに、その人が生活する社会や文化によって、その人の見え方も診断結果も変わってくるのです。障害は個人が作り出すものではなく、個人と環境との相互作用の中で育ってしまうものなのです。
特性を「治す」のではなく、その特性によって生じる生活上の困難さをなくしていくことが大切なポイントです。

発達障害は現代病? 増えているって本当?
結論から言うと、発達障害特性を持つ人の割合は、昔から大きな変化はないのだそうです。どうやら、その特性を持つがゆえに社会生活を持つことが難しいという人を「現代病」と名指してしまうような社会の側に問題があるよう。そもそも、20年前と今とで「発達障害」という言葉が指す医学的な概念はまったく異なり、厳密な比較は不可能です。よって、特性としての遺伝的素因を持つ人の割合に大きな変化はないと考えられているのです。
もし、子どもの発達に不安や疑問を感じたときは、自治体の発達相談窓口を訪れ、必要となれば発達検査・知能検査を受けましょう。
ただ、発達段階の評価でどんな数値が出たとしても、それはあくまでも“子どもの今の実体を客観的に把握し、数年後のあるべき姿を考える手がかり”にすぎません。信頼できる支援者からのアドバイスにはぜひ耳を傾け、数値に振り回されすぎないことを心がけていただくとよいでしょう。
結果のよしあしというよりも、「これからどうするか」を専門家とともに考えていくことが大切なのです。

文=矢島史
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」
Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細