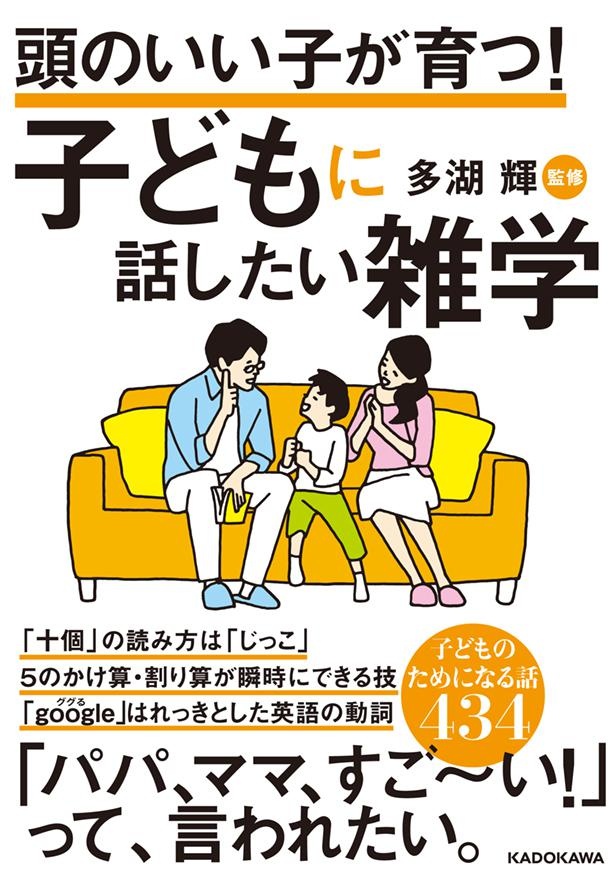マグロのトロは手頃な「庶民食」だった? トロが高級品になったのはいつからか/子どもに話したい雑学(17)

子どもに今すぐ話したい「タメになるうんちく」!
「一晩置いたカレーがおいしくなるのはなぜ?」「ポン酢のポンってなに?」
これ、答えられますか?
「子どもにすごいって思われたい」「日々のコミュニケーションの中で色んなことを教えてあげたい」そんな方に、わかりやすく、楽しみながら「タメになるうんちく」をご紹介。
それでは、学校では教わらないけれど子どもに話したい雑学を見ていきましょう!
※本記事は多湖輝監修の書籍『頭のいい子が育つ! 子どもに話したい雑学』から一部抜粋・編集しました
マグロのトロは手頃な「庶民食」だった
マグロは、日本人が愛してやまない魚である。赤身はもちろん、特に口の中でとろける食感がたまらない「トロ」は、味もさることながら値段も高級な食材として知られている。しかし、トロが高級食材として重宝されるようになったのは、そう昔の話ではない。
マグロが日常的に食されるようになったのは江戸時代後期のこと。おもに赤身をしょう油に漬けた「ヅケ」が、寿司ネタとして出回っていた。ただ、当時マグロは「シビ」と呼ばれていて、「死日」を連想するとして武士の間では忌いみ嫌われる存在だった。
現代の高級食材トロはといえば、脂が多いために冷凍技術のなかった時代には保存がきかず、すぐに捨てられることもあった。日本人の味覚の変化もあって、トロが好まれるようになったのは、昭和に入ってから。この頃になってもトロの値段は安いままで、庶民にとってはありがたい食材だったのだ。
現代のように、トロが高級なものとして崇められるようになったのは第二次世界大戦後のことである。
監修=多湖 輝/「頭のいい子が育つ! 子どもに話したい雑学」(KADOKAWA)
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「SILTEQ「きれいのミカタ 丸めて煮沸除菌できるまな板 Mサ…」
クルッと丸めて電子レンジや煮沸で簡単除菌! 刃あたりソフトで使いやす…
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細