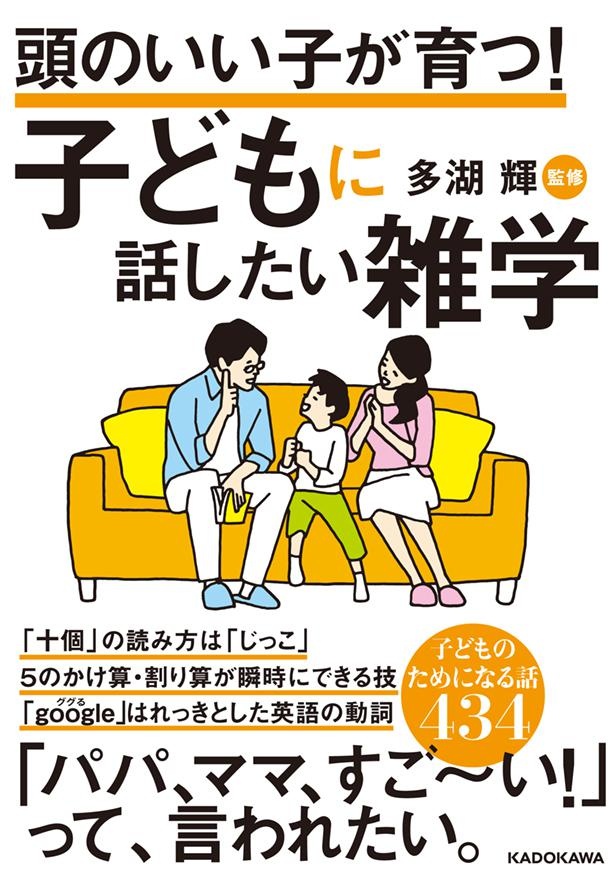和食器は5組1セット、洋食器は6組1セット。数が違う理由って?/子どもに話したい雑学(59)

子どもに今すぐ話したい「タメになるうんちく」!
「一晩置いたカレーがおいしくなるのはなぜ?」「ポン酢のポンってなに?」
これ、答えられますか?
「子どもにすごいって思われたい」「日々のコミュニケーションの中で色んなことを教えてあげたい」そんな方に、わかりやすく、楽しみながら「タメになるうんちく」をご紹介。
それでは、学校では教わらないけれど子どもに話したい雑学を見ていきましょう!
※本記事は多湖輝監修の書籍『頭のいい子が育つ! 子どもに話したい雑学』から一部抜粋・編集しました
和食器と洋食器の1セットの数が違う理由
結婚式の引き出物でもらった和食器のセットは、5組で1セット。以前、別の式でもらった洋食器は確か6組だったような気が……。どうして微妙に数が違うのだろうか。
日本では、奇数が縁起がいいとされている。
陰陽道で奇数は「陽」、偶数は「陰」で、3月3日(桃の節句)、5月5日(端午の節句)、9月9日(重陽)……と、節句はすべて奇数の重なりだし、御祝儀や香典を包むときも奇数にするのがマナー。例外は末広がりで縁起のいい8(八)だ。食器のセットが5組なのは、現代の家族構成を考えた適切な数だからだろう。
一方、西洋では物を数えるのに12進法を使ってきた。
12で1ダース、それが12集まると12×12=144で1グロスとなる。
また、西洋の社交は夫婦単位で行なわれるため、奇数では半端が出てしまう。正式な食器のセットは現代でも12組だが、それでは一般家庭では多すぎる。そのため、6組で1セットとしたのである。
監修=多湖 輝/「頭のいい子が育つ! 子どもに話したい雑学」(KADOKAWA)
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「SILTEQ「きれいのミカタ 丸めて煮沸除菌できるまな板 Mサ…」
クルッと丸めて電子レンジや煮沸で簡単除菌! 刃あたりソフトで使いやす…
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細