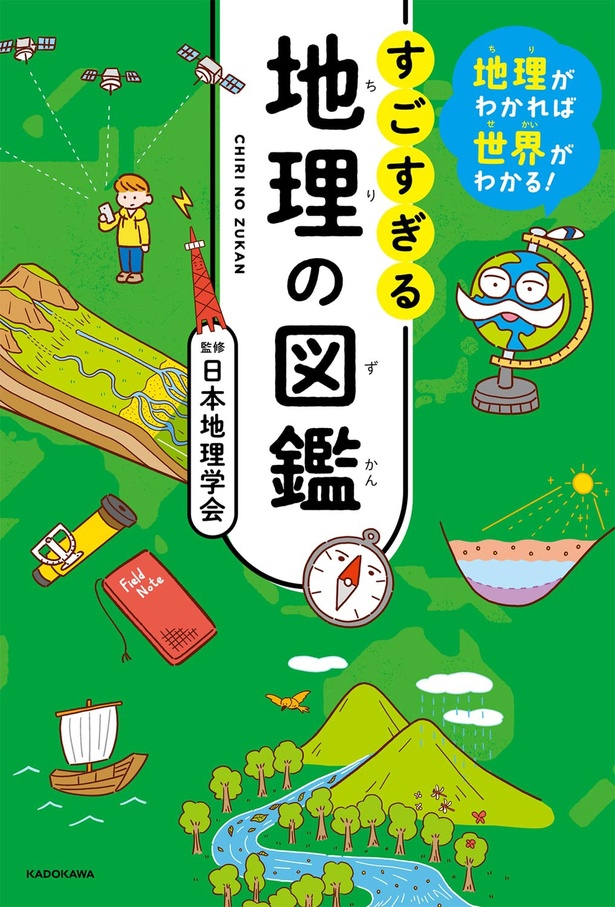人気観光地「江の島」は「島」なのに陸続き?/すごすぎる地理の図鑑(3)

普段ニュースで見聞きする政治や経済、観光地にグルメ。実はこうした様々な情報がすべて「地理」につながっているって、知っていましたか? 地理の勉強は、地名を暗記したり地図を眺めるだけじゃないんです!
地図からわかる地域の自然環境や歴史、暮らしぶりなどは、地理を学ぶとその背景や理由、意外な事実が見えてきて、ぐっと理解が深まります。地理は「地域の謎を解くカギ」と言える、とても身近で面白い学問なのです。
世界のことが今よりもっとわかるようになる、地理のネタあれこれをお届けします。
※記事の情報は2023年3月現在のものです。
※本記事は日本地理学会著の書籍『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』から一部抜粋・編集しました。
「江の島」は陸続きなのにどうして「島」と呼ばれる?
江の島は神奈川県の湘南海岸にある小さい島で、観光地としても多くの人に愛されています。江の島は満潮のときには島ですが、干潮のときは陸とつながります。江の「島」というのに、なぜ陸続きになるのでしょうか?
このように陸につながっている島を陸繫島(りくけいとう)といい、陸と島をつないでいる部分の地形はトンボロと呼ばれます。元々は島ですが、島の周りの波や海流の影響で砂が溜まり、陸続きになるのです。陸と島の間がそれほど離れていなくて、陸と島の間の水深が浅いところにできる地形です。このような地形は江の島だけではなく、日本中のいろいろなところで見ることができます。
波や海流の影響で砂が溜まってできる地形の呼び名は、場所や形によって変わります。陸地の岬から海に向かって細長く突き出た砂の部分のことを砂州(さす)といいます。これが島につながればトンボロ、海流の方向により嘴のように曲がっていれば、砂嘴(さし)と呼ばれます。
海流や風がつくり出す砂浜のいろいろなかたち

さまざまな砂浜の地形
川の上流から流されてきた石や砂が、風や海流に運ばれて、海岸線にいろいろな砂の地形をつくり出す。基本形は「砂州」で、条件によって「砂嘴」や「トンボロ」と呼ばれる。トンボロの先には必ず「陸繫島」がある。

【トンボロ】 【陸繫島】
神奈川県 江の島
江の島は境川(片瀬川)が運んできた土砂や湘南海岸を流されてきた砂が、島の周りに溜まって陸続きになった陸繫島。トンボロは普段は海中にあるので、干潮時のみ見ることができる。

【トンボロ】 【陸繫島】
フランス モン・サン・ミシェル
フランスの西海岸、サン・マロ湾上に浮かぶ陸繫島に建てられた修道院。同じく陸繫島の江の島は、日本のモン・サン・ミシェルともいわれる。

【砂州】
京都府 天橋立
日本海から宮津湾に流れ込む対馬海流が運んできた砂礫がたまり、できた砂州。宮城県の「松島」、広島県の「宮島」と並ぶ日本三景のひとつ。

【砂嘴】
北海道 野付半島
砂礫が溜まってできた砂州が海流により、嘴のように曲がった地形を砂嘴という。野付半島は根室海峡の海流でできた延長26kmにわたる日本最大の砂嘴である。
豆知識
波には、海岸を侵食し、砂礫を移動させるような強い力があります。これにより、さまざまな海岸地形を見ることができます。海岸の岩石が硬いかもろいかにより、見られる地形も異なります。
著=日本地理学会/『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』
Information
おすすめ読みもの(PR)
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細