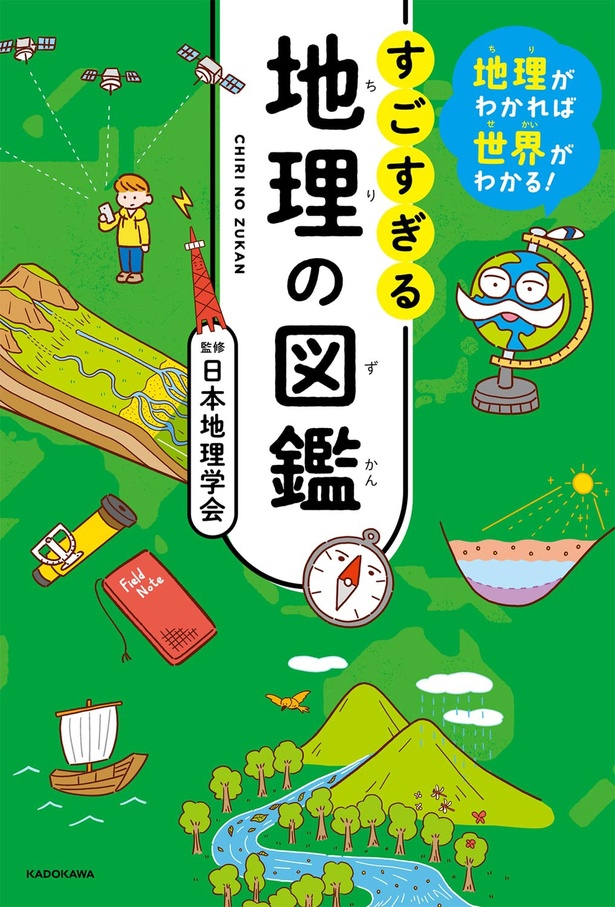通称「塩の道」や「鯖街道」。かつて食材の運搬ルートが決まっていた理由とは/すごすぎる地理の図鑑(6)

普段ニュースで見聞きする政治や経済、観光地にグルメ。実はこうした様々な情報がすべて「地理」につながっているって、知っていましたか? 地理の勉強は、地名を暗記したり地図を眺めるだけじゃないんです!
地図からわかる地域の自然環境や歴史、暮らしぶりなどは、地理を学ぶとその背景や理由、意外な事実が見えてきて、ぐっと理解が深まります。地理は「地域の謎を解くカギ」と言える、とても身近で面白い学問なのです。
世界のことが今よりもっとわかるようになる、地理のネタあれこれをお届けします。
※記事の情報は2023年3月現在のものです。
※本記事は日本地理学会著の書籍『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』から一部抜粋・編集しました。
塩の道、砂糖の道、鯖の道 ルート選びは必然だった!
日本各地には、さまざまな食材を運ぶために使われていた道があります。
これらの道を観察してみると、活断層沿いや、低地、平野部など、山がちな日本の中の歩きやすい場所を選んでいることがわかります。そのひとつが千国街道、別名塩の道。新潟の糸魚川から長野の松本に至る道で、ここは糸魚川―静岡構造線と呼ばれる断層が日本を南北に縦断する場所です。
砂糖は、江戸時代の日本は鎖国していましたが、長崎の出島では、オランダと交易をしていました。18世紀中頃から砂糖が大量に輸入されるようになり、出島から長崎街道を通って福岡の小倉まで運ばれました。これがシュガーロードです。
若狭湾の港町から京都まで魚介類を運んだ道は鯖街道と呼ばれ、そのひとつである福井の小浜と京都の大原を結ぶ若狭街道は、小浜から保坂が熊川断層、保坂から大原が花折断層と一致します。断層の活動でもろくなった岩盤は削りやすく、そこに道を整備したためだといわれています。
断層は道をつくってくれた

(1)塩の道

千国街道
塩の道は、糸魚川-静岡構造線の断層に沿ってできた道だった。

(2)鯖街道

若狭街道
若狭街道は、比良山地と丹波高地間の花折断層上につくられた。

(3)シュガーロード

長崎街道
海外から砂糖や菓子の技法などが流入し、銘菓も生まれた。

※海岸線は近世末期の状態を復元したものです。
豆知識
信濃国に運ばれた塩は、日本海側からのものは「北塩」、太平洋側からのものは「南塩」と呼び分けられました。長野県の塩尻という地名の由来は、一説によると塩の道の末端という意味があるともいわれます。
著=日本地理学会/『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』
Information
おすすめ読みもの(PR)
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細