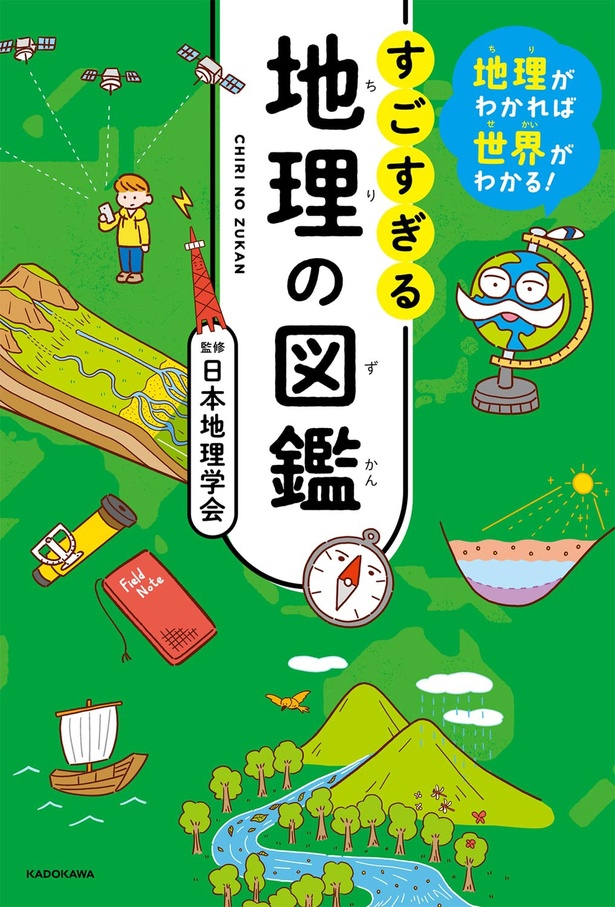日本国内シェア9割! 静岡県がプラモデルの一大産地になったワケ/すごすぎる地理の図鑑(7)

普段ニュースで見聞きする政治や経済、観光地にグルメ。実はこうした様々な情報がすべて「地理」につながっているって、知っていましたか? 地理の勉強は、地名を暗記したり地図を眺めるだけじゃないんです!
地図からわかる地域の自然環境や歴史、暮らしぶりなどは、地理を学ぶとその背景や理由、意外な事実が見えてきて、ぐっと理解が深まります。地理は「地域の謎を解くカギ」と言える、とても身近で面白い学問なのです。
世界のことが今よりもっとわかるようになる、地理のネタあれこれをお届けします。
※記事の情報は2023年3月現在のものです。
※本記事は日本地理学会著の書籍『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』から一部抜粋・編集しました。
静岡県がプラモデルの聖地になった地理的な理由
日本のプラモデルのじつに9割が、静岡県でつくられていることを知っていますか? 特に静岡市周辺にはプラモデル工場が多く、市は「模型の世界首都」とうたっています。なぜ静岡県がこれほどのプラモデルの産地になったのでしょうか。
その理由を探るには、江戸時代までさかのぼる必要があります。江戸時代初期、幕府直轄領(天領)の駿府(現在の静岡市)では、久能山東照宮の造営や静岡浅間神社の社殿再建など、幕府の威信をかけた国家事業が実施されました。このときに全国から集められた腕のよい職工が、その後駿府に残り、タンスなどの木製品をつくり始めます。
安倍川上流などから切り出される良質な木で木製品の産地となりますが、生産過程で大量の木片が捨てられます。その木片を有効活用したものが、木製模型です。1950年代にさまざまな製品の素材がプラスチックに変わるなかで、木製模型もプラモデルに転換していったのです。
プラモデルの9割以上が静岡県でつくられている!

静岡市にあるプラモデルを模した郵便ポスト
プラモデルにポストが埋め込まれている! いろいろなかたちで〝プラモデルの街〝をアピールしている。
都道府県別プラモデルの出荷額
(2019年/単位は百万円)

製品の産地と都道府県別シェア(2019 年)

豆知識
上に示したように地域の産業がどのように発生し、発展し、いまどうなっているのかを研究することは、経済地理学の主要なテーマのひとつです。みなさんの住む地域にはどんな産業があるでしょうか?
著=日本地理学会/『地理がわかれば世界がわかる! すごすぎる地理の図鑑』
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」
Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細