「産まない女性」やLGBTが人類生存の可能性を広げる!? 男女のミゾを科学する(3)
第三の脳
ただし、脳の性差は、必ずしも身体の性差と一致するわけではない。少数派ながら、男性の身体に、女性脳的感性を選択する脳が搭載されている場合もある。
それは、マジョリティの男性とも女性とも違う第三の脳であり、太古の昔から一定数生まれてきている。だとするならば、それもまた、人類の戦略の一つだと言えるのではないだろうか。マジョリティとは違う脳が一定数混じることで、人類は、その生存可能性を広げてきたはずである。
本連載では、マジョリティの男女間で起こるコミュニケーション・ストレスを論じるが、マイノリティの感性を排除しているわけではない。
むしろ、マイノリティの方たちは、その感性を強く使っていたりする。私のゲイの友人たちは、私なんかよりずっと女性脳的な使い方をする。あくまでも「脳の性差」で読んでいただくと、LGBTの方や、そのパートナーにも参考にしていただけるはずである。
ちなみに、男性が女性脳的感性の使い方をする(共感し、危機回避能力が高い)からと言って、必ずしも性的嗜好が反転するわけじゃない。
男らしく生きながら、繊細なプロセス解析力を持ち、直感的な判断がうまくできるタイプもこれに含まれる。
産まない女性は、未完成などではない
「産まない女性」についても一言。
「子どもを産んで、女は一人前」のような言い方をする人がいるが、それは違う。
たしかに、妊娠・出産・授乳によって、女性の脳は、ホルモンの劇的な変化に見舞われて位相を変え、うまくいけば、繊細さとタフさを兼ね備えることになる。さらに、子どもに、自分の資源(時間、意識、手間)のすべてを捧げるために、かなり偏ったものの見方をするようになる。大切なものへの共感力を極限まで上げるのだ。この能力がなければ、子どもは育て上げられない。この能力は、仕事においては、顧客や市場への共感力として、効を奏することも多い。
しかし、産まない女性の時間だって止まっているわけじゃない。脳には、出産子育て以外の経験が降り積もっていく。その経験が、彼女たちを繊細にしてタフにしていく。
産まない女性は、公平さを保ったまま成熟していく。女性が生まれつき持っている母性の機能を、周囲に照らすように公平に使えるのである。多くの組織で、産まない女性たちが、組織を束ねる要になったりしている。昔から、世界中の宗教が生まない女性を確保してきたのには(シスター、尼僧、巫女(みこ)など)、きっと理由がある。
女性脳型の感性の使い方の典型例として、子育て中の女性を例に挙げることもあるが、それは、「使い方が振り切った例」として便利だからだ。けっして、産まない女性を排除しているわけではないことを、ここで述べておきたい。
著=黒川伊保子/「コミュニケーション・ストレス 男女のミゾを科学する」(PHP研究所)
Information
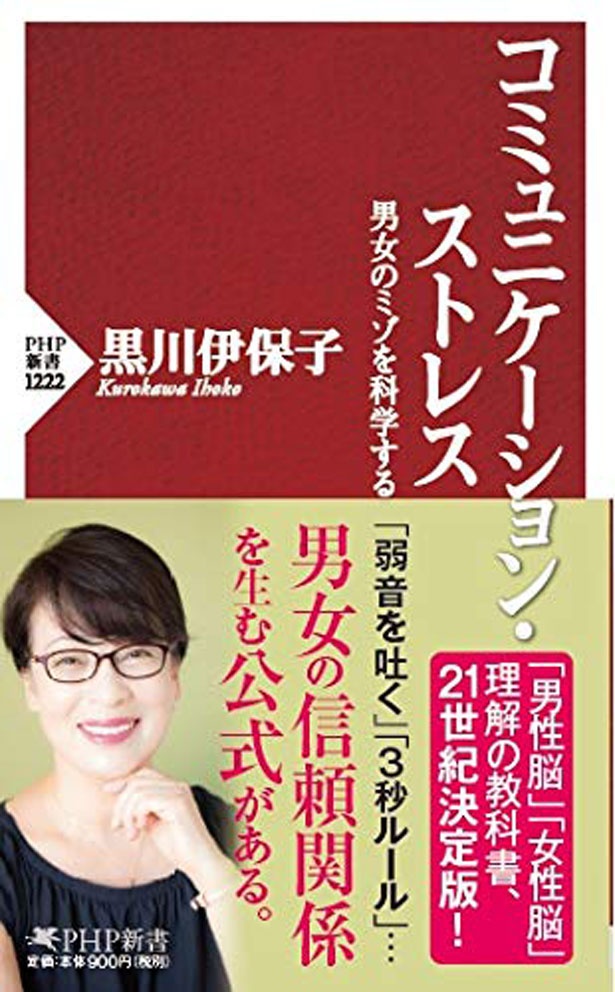 『コミュニケーション・ストレス 男女のミゾを科学する』
『コミュニケーション・ストレス 男女のミゾを科学する』
職場での行き違いや夫婦の仲違いが生まれる前に、多く発生しているのが男女のコミュニケーション・ストレス。その発生する仕組みやギャップを乗り越えるヒントをまとめた教科書が登場しました。『妻のトリセツ』が大ベストセラーとなった人工知能研究者が、メーカーで人工知能(AI)開発に携わったキャリアを生かして著した、コミュニケーションテキストの決定版です。
▼amazon▼
▼楽天ブックス▼
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」
気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細


















