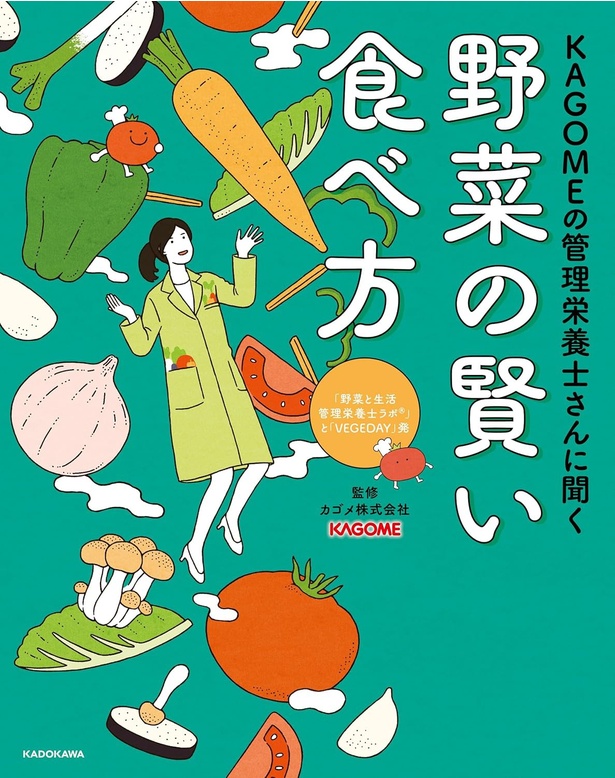【KAGOMEの管理栄養士さんに聞く】日持ちしやすくビタミンC豊富! ピーマンの苦みはどう抑える?/ 野菜の賢い食べ方(2)

日本有数の食品・飲料メーカーであるカゴメの管理栄養士チーム「野菜と生活 管理栄養士ラボ(R)」をご存知ですか?
野菜に関する研究で得た知見を活かし、野菜摂取の重要性や上手な摂り方を伝えるセミナー、特定保健指導、レシピ・コラムの監修など、多岐にわたる活動を行っている、カゴメの管理栄養士による専門チームなんだとか。
そんな専門家たちによる、栄養を余すことなくいただける賢い野菜の食べ方をご紹介します。
※本記事はカゴメ株式会社監修の書籍『KAGOMEの管理栄養士さんに聞く 野菜の賢い食べ方』から一部抜粋・編集しました。
ピーマンは日持ちしやすくビタミンC豊富!苦みは2つのテクニックでカバー

POINT
・選ぶときは、表面に傷がついていないかチェック
・緑ピーマンは種もワタも食べられる!丸ごと煮がおすすめ
一般的に出回っている緑ピーマンは、青く未熟な状態のうちに出荷されるため、苦みが強いのが特徴です。完熟すると赤くなって甘みが増し、青臭さが抜けて食べやすくなります。
一方、緑ピーマンは未熟だからこそ日持ちしやすいというメリットも。冷蔵庫で2週間ほど保存できる場合もあります。ピーマンの一種である肉厚で大きなパプリカは、赤や黄色、オレンジ色のものが一般的ですが、実は紫、茶、黒などの種類もあり多彩です。
長く置いておくと皮が硬くなってしまうため、丸ごと保存するときは、1個ずつキッチンペーパーで包んで保存袋で冷蔵し、1週間を目安に使い切りましょう。
from 野菜と生活 管理栄養士ラボ
ビタミンCといえば、レモンやレタスをイメージする方が多いのではないでしょうか? ですが、ピーマンのビタミンC含有量は、野菜のなかでもトップレベル。ほかに、β-カロテンやビタミンEなども豊富です。
苦みがあるので苦手なお子さんは多いのですが、学校給食の献立を作る管理栄養士としては、健康のためになるべく使いたい食材のひとつ。ご家庭でも工夫して取り入れてみてくださいね。
【食べ方アイデア】ピーマンの苦みは切り方と油でカバー

ピーマン特有の苦みをカバーするコツのひとつは、繊維に沿って縦方向に切ること。逆に、輪切りのように横方向に切ると、繊維が断たれて苦み成分が出やすくなってしまうので注意しましょう。2つ目は、油と一緒に調理すること。
周りが油でコーティングされることによって、苦みを感じにくくなります。加えて、お子さんの好きなトマトケチャップ味やカレー味などに調味してあげると、よりお箸が進みやすくなるでしょう。
【簡単レシピ】パプリカはトロッと甘い丸ごと焼きに!

丸ごとこんがり焼いて
パプリカを簡単においしく食べるなら、丸ごと焼きがおすすめです。魚焼きグリルやトースターなどで皮が真っ黒に焦げるまで焼いたら、すぐ氷水に取って表面の皮をむきます。すると、甘みが増して食感もトロッと大変身!
オリーブ油と塩・こしょうなどをふっておつまみにしたり、肉を炒めるときに加えたりして楽しんで。まとめて数個焼き、裂いた状態で冷凍すれば、1ヶ月ほど活用できます。
RECIPE
ピーマンの保存方法
保存するときは洗わずに、水気があれば拭き取ってから、ポリ袋に入れて口を閉め、冷蔵庫の野菜室へ。調理の際は、食べる分だけ袋から取り出して。
ピーマンは切り口から傷んでいくので、できるだけ1個を使い切りたいものです。また、赤ピーマンはすでに完熟しているため、特に傷みやすいので気をつけて。
ピーマンのツナ卵炒め(2人分)
マヨネーズをかけて丼に、パンに溶けるチーズと一緒にのせて焼けばピザ風にアレンジすることもできます。

作り方
1 ピーマン5~6個は種とワタを取って縦に細切りにする。溶き卵2個分は粉チーズ小さじ1(お好みで)を混ぜて卵液を作っておく。
2 ツナ缶の油(適量)をフライパンに入れて熱し、ツナ1缶(80~100g)とピーマンを炒める。
3 めんつゆ(ストレート)大さじ1 と砂糖小さじ1を合わせておく。
4 3を2に入れ、ピーマンがしんなりとしてきたら1の卵液を入れて炒める。
記事を参考にするときは
・本記事の野菜の栄養価は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)に記載されている原材料『生』の成分値を用いて算出しています。
・本記事に記載するβ-カロテンの値は、β-カロテン当量を採用しています。
・医師の指示のもと栄養指導を受けている方は、必ずその指示・指導に従ってください。
・本記事で使用している大さじ1は15ml、小さじ1は5mlです。ひとつまみ、少々は親指と人さし指の2本でつまんだ量が目安ですが、個人差があるので味を見ながら調節してください。
・本記事に記載する保存期間は目安です。調理器具の衛生状態や食材の状態、ご家庭の保存状態や季節などにより異なる場合があります。食べる前によくご確認ください。
監修=カゴメ株式会社/『KAGOMEの管理栄養士さんに聞く 野菜の賢い食べ方』
Information
おすすめ読みもの(PR)
プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」
Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…
メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!
新規会員登録する
読みものランキング
読みものランキングをもっと見る
レシピランキング
レシピランキングをもっと見る
レタスクラブ最新号
レタスクラブ最新号詳細