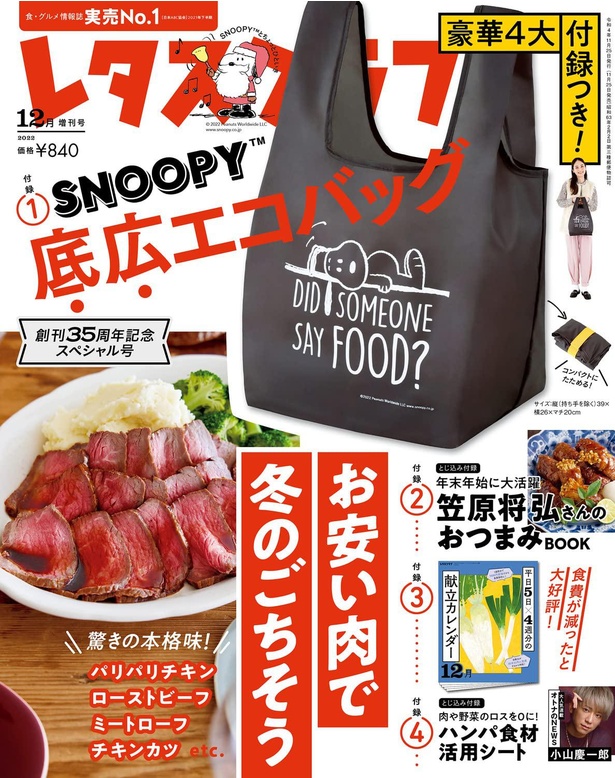永遠のテーマ「子どもスペースの収納」!すっきりさせるコツはひとつ
こんにちは。
整理収納アドバイザーのまあちです。
日々の暮らしや整理収納、家事ラクアイデアなどを発信しています。
Instagramでは10万人以上の方々にフォローしていただいています。
今日はよくご質問をいただく、子どものおもちゃ、作品の収納についてご紹介します。

我が家には小学校2年生の息子が一人います。
お子様が多いと部屋をスッキリさせるには、よりいっそうモノの数を厳選したり収納に工夫が必要になりますが、基本的な考え方は同じです。
1.おもちゃ収納

乳幼児期(文字が書ける前)は写真で片付け場所をラベリングしていました。
この時も親がパパッと一人で決めてしまうのではなく、子どもがお話出来るようになってからは、
「ここにしよっか。どうかな?」など子どもに声をかけながら一緒に考えていくことが大切です。

子どもが文字を読めたり、書けるようになってからは本人がラベリングを作成しました。
本人が書いてみたい!やってみたい!と思ったタイミングで出来るとベストです。
親はあくまでサポート役、ここはあなたのスペースだよ。と思ってもらうことが大切です。

子どもが小学校1年生の時は、全て文字のラベリングに変わっていました。

ガチャガチャやオマケのおもちゃなど細々したモノが何かと増えることってありますよね。
そういうおもちゃの収納は、ひとまずボックスを作っておくと便利です。溜まってきたら、見直すゾーンです。

ぬり絵やお絵描きは100円ショップのケースに収納。
2.作品収納

保育園や小学校でたくさんの作品を作ってきますよね。
それらの保管に頭を悩ませている親御さんも多いです。
なんでも残したくなりますが、我が家では立体作品と平面作品に分けて、それぞれ1ケースまでと決めています。

セリアのラベルホルダーを貼っています。
(おもちゃ収納のラベリングでもこちらを愛用)

作品BOXは「towerの作品収納ボックス 2個組 ホワイト」です。
このように年齢によっても、収納方法は変わっていきます。
大切なのは幼い頃から、ここはあなたのスペース。という認識をもってもらうこと。
親がやった方が早いですが、そこはぐっと我慢してサポート役になります。
そうするとある程度の年齢になってくると、自分で出来るようになる確率が上がるのです。
とはいえ散らかっていても気にならない、という性格の子もいますし(それは大人も同じ)多少散らかっていても「まぁいいか。」という懐の大きさも必要ですよね。
これがなかなか難しいのですが。
何か一つでも参考になれば嬉しいです。
作=まあち
まあち

▶voicy:
暮らしが整うラジオ▶Instagram:
@maachi.k.k_homeInformation
関連記事
おすすめ読みもの(PR)
ピックアップフレンズ
フレンズをもっと見る
「フレンズ」レポ一覧
「フレンズ」レポランキング
「フレンズ」レポランキングをもっと見る